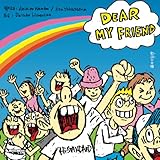ニュース
LINEヤフーが2000人に調査、半数以上が「偽・誤情報の影響を受けている可能性がある」と回答
2025年7月1日 09:00
LINEヤフー株式会社は、Yahoo!クラウドソーシングユーザー2,000人を対象に行った、インターネット上の偽・誤情報に関するアンケート調査結果を公表した。
総務省がまとめている『インターネットとの向き合い方~ニセ・誤情報にだまされないために~第2版』では、偽情報は「意図的・意識的に作られたウソや虚偽の情報」で、誤情報を「勘違いや誤解により拡散した間違い情報」と定義している。
同調査によると、「これまでに偽・誤情報を見聞きしたことがあると思う」と回答した人は87%に上っている。見聞きした偽・誤情報のジャンルとしては、「芸能・スポーツ」(31%)が最多で、次いで「政治」(18%)、「医療・健康」(10%)という結果となった。
偽・誤情報だと判断した理由を聞いたところ、「情報に接してから調べて確認した」という人(42%)が最も多く、次いで「自身の経験や知識から判断した」人が37%となっている。
「自身が偽・誤情報の影響を受けている可能性があると思うか」という設問には、54%の人が「あると思う」「多分あると思う」と回答した。
影響の具体例としては、「健康に良いらしいと見聞きした食品を試した」「不足するかもしれないと見聞きした商品を買いだめした」「真偽不明の情報で選挙時の投票先を考えてしまう」「情報の精査で時間を浪費している」など、さまざまな内容が挙げられている。
「偽・誤情報に関する啓発や情報提供は十分だと思うか」という設問では、88%の人が「不十分だと思う」と回答。有効な啓発や情報提供として「学校の授業で教えてほしい」という意見のほか、「ファクトチェックの普及」や「自分でできるファクトチェックの方法を提供する」といったファクトチェックの充実に関する意見も多数見られた。
また、発信者側に対するアクションとして、「発信者がしっかり責任を負うべき」「虚偽情報の発信は、場合によって犯罪になり得るということがもっと知られてほしい」といった声も寄せられている。
LINEヤフーでは、正確な情報発信やリテラシー向上のための啓発を行っており、「Yahoo!ニュース コメント欄」や「Yahoo!知恵袋」「LINEオープンチャット」といった投稿型サービスでは、モニタリングや注意喚起、違反投稿削除、通報機能などを組み合わせた偽・誤情報対策を実施。明らかな偽・誤情報と判断されるものについては、投稿を禁止している。
Yahoo!ニュースの特集記事「あなたは大丈夫? 選挙で気をつけたいネットリテラシー」では、注意すべき点を以下のようにまとめている。
・情報源を確かめる……どこから出てきた情報? 誰の発信?
・情報が発信された日を確かめる……最初に発信されたのはいつ?
・意見なのか事実なのかを確かめる……誰かの意見? 引用や伝聞形式の中身は事実?
・複数の情報源で見比べる……公式情報やほかのメディアはどう伝えている?










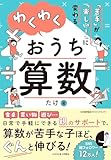

















![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)