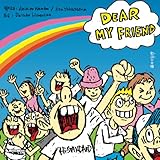レポート
教育実践・事例
AIに頼ると考えなくなる? 実践者が語る「授業の目的」と人間中心のAI活用
教育AIサミット 実例大全レポート①
2025年5月13日 06:30
急速に進歩する生成AIは、教育現場において学びの個別最適化や創造性の向上、思考力の支援を実現する強力なツールとなり得る。子供たちの学びをより豊かにするためには、AIを学びの相棒やパートナーとして、その使い方のみならず、避けては通れないリテラシー教育、そして何よりも教育活動の目的設定を明確にすることが不可欠である。
本稿では、2025年3月にコクヨ東京品川オフィス THE CAMPUSにて開催されたイベント「教育AIサミット 実例大全」(主催:一般社団法人教育AI活用協会)より、青山学院中等部 情報教育担当講師 安藤昇氏、東京学芸大学附属小金井小学校 教諭 鈴木秀樹氏、札幌国際大学 准教授 安井政樹氏の3名による講演を取り上げる。教育現場の最前線でAI活用に取り組む実践者の声を通して、AIと人間が協働し、教育効果を高めるための具体的な方向性を探る。
バイブコーディングで中学校のプログラミング授業は一変、倫理観の育成が急務

青山学院中等部で情報教育を担当する安藤昇氏は、AIが生徒の創造性を刺激する実践として、「Vibe Coding(バイブコーディング)」を紹介した。
Vibe Codingとは、Vibe(雰囲気・感覚)とCoding(コーディング)の造語で、生徒が自然言語で「なんとなく」作りたいものを指示すると、AIが対話的にコード生成から動作確認まで行うプログラミングの手法だ。例えば、「スーパーマリオみたいなゲームを作って」という指示を行うと、AIが要件を整理し、HTML、CSS、JavaScriptコードを生成。さらにAIエージェントが実際にゲームをプレイしてデバッグまで試みる、というデモンストレーションが行われた。「今までのプログラミングの授業では10分で飽きていた生徒が、バイブコーディングの手法であれば2時間ぐらいずっと集中するようになった」と安藤氏は手応えを語る。従来のプログラミング学習でつまずきがちだった生徒の意欲が大幅に向上したという。
安藤氏はさらに、Claude 3.7 SonnetやChatGPT o3 miniなど複数のAIの特性を理解し、互いを連携させることで、より高度なアウトプットを引き出す方法も披露。生徒は、自分が指示したゲームとは似て非なるAIが生成したゲーム画面に「いやこれ全然違うし!」とツッコミを入れながら、目を輝かせて次々に改良を加えていくという。AIが単なる作業代行ではなく、生徒のアイデアを形にし、可能性を広げる「パートナー」となり得ることを示した。
しかし安藤氏は同時に、AIの急激な進化と使い方に伴う倫理的な課題も指摘する。高性能化したAIは、中高生でも容易に高度な技術にアクセスできる状況を生み出しており、「もはやハルシネーション(もっともらしい嘘をつく現象)対策といった次元の話ではない」と警鐘を鳴らす。
「例えば、私の生徒たちは高度な技術を使いこなせるようになっているが、それを悪用しないのは倫理観があるからだ」と安藤氏は語る。AIによって強力な技術が民主化された今、倫理教育の重要性が不可欠であることを強調した。
小学校国語科のAIによる個別最適化と、授業の目的設定の重要性

次に、東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木秀樹氏は、AIが「学びの個別最適化」をどのように支援できるか、具体的な実践を紹介した。
鈴木氏は、ICTを学習上の困難を抱える子供たちのサポートツールとして活用するインクルーシブ教育の観点から、AIを思考支援の領域にも応用している。「教科書を読むのがつらい、作文が難しい、といった子たちが、ICTを介することでうまくいくケースを多く見てきた。いよいよ思考部分でもAIが助けてくれるのでは」と、AI活用への期待を語る。
国語の授業「大造じいさんとガン」で「作品の魅力を文章でまとめる」活動を取り上げた際、「『面白い』としか書けない」「何を書けばいいかわからない」と手が止まってしまう児童がいる。こうした書くことに困難を感じる児童に対し、AIとの対話を通じて考えを整理し、文章化を支援した。AIが質問し、児童が答えや選択肢を選ぶことで、文章のたたき台が作られる仕組みだ。
ここで重要なのは、鈴木氏が強調する「授業の目的設定」である。「これまでの授業では、書くのが得意な子や理解が早い子たちだけを拾って『思考が深まりました』と評価しがちだった。でも、書けない子は思考が深まっていないのではないか」という問題意識から、「この授業の目的は、友達と話し合い考えを広げること。文章作成はそのための手段であり、AIの支援はその目的達成を助けるもの」と位置づけている。
結果として、従来は意見表明が難しかった児童も、AIが生成したたたき台をもとに自分の考えを加えられるようになり、 「AIの助けで同じ土俵に立ち、自信を持って話し合いに参加できるようになった」という。
また、保健の授業の「ケガの防止策」作りにおいては、AIが草案を作り、それを別のAIが評価・改善するという使い方を提示。児童自身にAIを使うかどうか、またどの段階で使うかを選べるようにしたという。先日行われた入学式のスピーチ作りでも、「『これは自分の言葉で書かなきゃ意味がないでしょ』とAIを使わない子もいれば、『AIでたたき台を作って手直しした方が早い』と考える子もいて、まさに自分で学び方を選んでいた」と、子供たちの主体的な選択の様子を紹介した。
このように、AIを活用することで、学習目標達成のための多様なルートを用意し、児童が自分に合った学び方を選択できる環境が実現しやすくなる、と鈴木氏はその意義を語る。
AIは子供の思考力を奪うのか?
両氏の実践紹介後のディスカッションでは、AI活用、特に「思考力や作文能力の低下」に対する教育現場の根強い懸念が議論された。
鈴木氏は、「AIに頼ると考えなくなる」という見方に対し、前述の国語の実践例を挙げ、「授業の目的が明確であれば、AIは有効な手段となり得る。文章を書くことが目的なのか、話し合うことが目的なのか。目的が明確なら、書くプロセスはAIに任せてもいいのではないか」と述べる。むしろ、「AIが生成した文章と自分の考えを比較・検討する過程で、より深い思考が促される可能性もある」と、AIとの対話が生む新たな学びの形を提案した。
安藤氏は、AI時代の思考力について、「正解を効率よく導き出す力」から、人間関係やジェンダー問題など、AIでは答えを出せない“答えのない問い”に対して、「多様な情報をもとに最適解や落としどころを見出す力」へと、求められる能力がシフトしていく可能性を指摘した。

モデレーターの安井氏も、「皆さんはご家族のスマホの番号、暗記してますか? ワープロが登場して漢字が書けなくなったから、使うのをやめましたか? それと同じではないか」と、道具と能力の関係性を分かりやすく例示。AIによって変化する能力もある一方、AIを駆使してより高度な課題解決に取り組む力が重要になるとの見方を示す。その上で、「AIは単なる“文房具”ではなく、人間の能力を引き出す“相棒”“パートナー”となり得る」と述べ、AIをいかに人間中心の視点で活用していくかが鍵であると議論をまとめた。
そのほか、AI活用を学校現場で推進する上での現実的な障壁である、管理職や行政、保護者の理解不足についても意見が交わされた。
鈴木氏は、反対意見に対して「まず文部科学省の生成AIガイドラインを参照してもらうこと」を勧め、ガイドラインが禁止だけでなく活用を後押しする側面も持つことを周知する必要性を述べた。保護者の懸念に対しては、安藤氏が「AIによる東大数学問題の解答デモ」など、学習効果や受験への有効性を具体的に示すアプローチを紹介。これに対し鈴木氏も効果を認めつつ、中学受験など、現行の評価システムとの間で保護者が抱えるジレンマにも触れた。
AIと共に拓く、未来の教育
このように、AIは児童生徒の創造性を解き放つ一方で、その利用には倫理的な教育と配慮が欠かせない。また、個別最適化された学びを支援する強力なツールとなり得るが、思考力の低下に対する根強い懸念にも丁寧に対応する必要があるだろう。
両氏の実践は、AIを教育目標達成のための「道具」そして「パートナー」として位置づけ、常に人間中心の視点で教育の本質に立ち戻る重要性を教えてくれる。教員は授業の目的を常に問い直し、AIの特性を理解した上で最適な使い方を模索し、子供たちが主体的に学び方を選択できる環境を整えることが求められる。文科省のガイドラインなどを共通の土台としながら、各教育現場での知恵と経験を積み重ね試行錯誤を続けていくことこそが、未来の教育を拓く道筋となる。














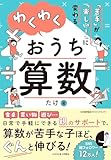

















![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)