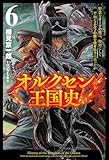トピック
小学生がEDIXを取材!生成AIのレポート改善アドバイスに子供たちの反応は…?
- 提供:
- 日本マイクロソフト株式会社
2024年5月22日 06:30
大勢の教育関係者でにぎわう「第15回EDIX(教育総合展)東京」の展示場。そこへ、小学生がやってきた。児童たちがブースを取材してまわり、その内容を公開授業で発表するという。しかも、取材内容をまとめたレポートに生成AIを使ってアドバイスをもらうというのだ。2024年5月9日、日本マイクロソフト株式会社の展示ブースで実施された公開授業の様子をお届けしよう。
小学5年生が取材に挑戦、いざEDIX会場へ
この日、EDIX東京の会場である東京ビッグサイトにやってきたのは東京学芸大学附属小金井小学校の5年生。学校から会場までバスで移動してきた。今日の活動は、「小金井小にあったら学校や授業がもっとよくなる製品を探そう」というテーマのグループワークで、会場を自由に歩きまわって取材をする。
児童たちは展示マップを手に、気になる会社名のブースに行こうと相談しつつも、歩いていると色々な展示品が目に留まり、次々と立ち寄って話を聞いていく。まず取材の説明をして許可をもらったら、「何の会社ですか?」、「何を作っているんですか?」と早速質問を投げかける。ブースに立つ担当者は児童の訪問に驚きつつも、わかりやすい言葉で説明してくれた。大人でいっぱいの展示会場だが、そこだけ少し空気がやわらかい。
グループでは、話を聞く人、メモを取る人、写真を撮る人など役割が決まっている。記録係は、普段から使い慣れている「Surface Go 3」を持ち歩き、聞いた話を書き留めたり、資料や展示品を撮影したりしていった。キーボードをはずしてタブレットとして使っている児童もいれば、キーボードをつけたまま持ち歩いたり、メモはノートに手書きという児童もいて、それぞれ使いやすい手段を選んでいる。
写真や映像、音声、文章を記録するのも、それを元に後でレポートを作成するのも同じ端末上でできるのが、1人1台端末が生み出した子供たちの当たり前の学習環境だ。それがすっかり馴染んで自然と使いこなす姿が印象的だ。
これ知ってる! 使ったことある! で盛り上がる
いろいろな展示ブースを回る中で、児童が最初に目を留めたのは、画面で見てわかりやすいデジタル教材や普段から見慣れている製品などだ。漢字や算数などのデジタル教材をデモ機で試したり、使ったことがある教材やキャラクターを見つけて「あ!これ知ってる!!」と盛り上がる姿も。プログラミングの学習教材では「手を動かすとセンサーが反応して動きますよ」とプログラムの仕組みを説明してもらって実際に試し、「本当だ〜動いた!」とうれしそうに確認していた。
パソコンの周辺機器を扱うブースでは子供向けのタッチペンやキーボードを試し、「充電はどのくらい持ちますか?」という具体的な質問も飛び出した。児童自身が普段タッチペンを使っているからこその実感が伴う質問だ。自分が使っているタッチペンやマウスを出して見せる児童もいて、説明担当者もリアルな子供の声に驚いた様子だ。
初めて見る物、よくわからない物も質問する児童
展示には初めて見る物やよくわからない物もたくさんあるが、疑問はその場で解決できた。例えば、2つの映像をリアルタイムで合成するシステムの展示では、仕組みに興味を持って「カメラはどこについているんですか?」と質問して実演してもらった。また、何の展示なのかわからず、「これはどういうことですか?」と率直に聞いて「タブレットなどの中に入っているCPUって聞いたことある? それを作っている会社なんです」と説明を受けて納得する姿もあった。
子供たちは電子機器自体には慣れているので、様々な展示コーナーで初めて聞く説明でも「へぇ〜すご〜い」、「面白そう!」などと声を上げて、自分なりの視点で受け止めている様子だ。さらに、「なぜこの仕事をしたのですか」と働いている人の気持ちについて尋ねたグループもあった。
会場は広く、大きなフロアが二つの階に分かれているので、限られた取材時間で回るには時間配分も重要だ。「次はどこに行く?」「あそこも行きたいから…」「あと何分?」と声を掛け合い行き先を決めて移動していった。
エンターテインメント性の高い楽しい体験も!
展示の中には、レクリエーションや知育、運動など楽しい体験ができるものもある。児童たちもこの時ばかりは純粋に楽しんでいた。床に投影するインタラクティブなゲームを体験した児童は、「あれいいね! 雨の日でもサッカーができる!」とうれしそうに話していた。
どのグループも集合時間を気にしながら最後までたくさんの展示ブースを回って取材を終えた。今回の活動は限定的なものだが、会場内を巡る小学生の姿に「おや?」という様子で目を向ける来場者も多かった。会場にあふれる教育ソリューションの向こう側にいるのは、この子供たちだということを改めて感じさせてくれたのではないだろうか。
取材レポートはすぐにSwayでWebページにまとめる
お昼の時間を挟んで午後はいよいよ取材レポートをまとめながらの公開授業だ。日本マイクロソフトの展示ブースでは、生成AI「Microsoft Copilot」を活用した授業が行われるとあって、多くの見学者が集まった。
授業が始まると早速、5年生担任 鈴木秀樹教諭が児童たちに取材してきたばかりの情報を「Microsoft Sway」でまとめるように投げかけた。Swayはプレゼンテーションやレポートなどを直感的な操作で作成しWebページとして公開できるツールだ。簡単に操作できるので、児童が使用するハードルも低い。
作業が進む一方で、鈴木教諭は児童に取材の様子を尋ねた。電子辞書のウェブ版がとても印象に残ったという児童は、いかに便利な機能だったかということを捉えて端的に説明した。どの報告にも、新しい技術への驚きやコンテンツを体験したうれしさがにじみ出る。当初の「これが小金井小にあったら……」というテーマ以上に、それぞれの気持ちに強く印象に残る体験をしてきたようだ。
生成AI「Copilot」に取材レポートの改善点を聞いてみると……?
取材の様子を報告しあっている間に写真や取材メモを組み合わせたレポートがSwayで形になってきた。鈴木教諭は「このレポートをどのように改善したら良いかAIに聞いてみよう」と説明し、Copilotを開いた。マイクロソフトのCopilotは13歳未満の利用ができないため、授業では鈴木教諭がCopilotを使用する。
鈴木教諭は、児童たちがSwayにまとめたレポートのテキストを個別にCopilotに読み込ませて、「小学生が書いた紹介文です。直した方がいいところを教えてください」という趣旨のプロンプトと共に送信した。
例えばタッチペンに関する説明を書いた部分についてCopilotは「この紹介文はとてもユニークで小学生が書いたとは思えないですね」としつつも、具体的な修正ポイントと修正文案を示した。該当するグループの児童は、細かな指摘に「ちょっと負けた気がします」と発言した。
鈴木教諭が他のグループの文章についても次々にCopilotに投げかけていくと、「より自然な日本語表現にする」、「具体的な例を挙げる」、「言い換えて明確にする」、「より自信を持った表現に」などいろいろなポイントを挙げながら、それぞれの文章の修正案を示していった。
Copilotの修正提案について、そのレポートを作成したグループの児童に意見を聞くと、「全体的に難しい表現になっていて、言い方が大人向けになっている」とCopilotの提案に同意できないという声や、「アプリの名前まで変えられているから、それは変えない方がいいんじゃないか」と間違いを指摘する声などが挙がった。また、「(Copilotが作った文は)けっこういい文章だと思うけど微妙に納得いかない」と漠然とした思いを伝える児童もいた。
鈴木教諭は、児童たちの言葉を受け止めながら、「その納得がいかないところをグループで話し合って、どうやって直すかを相談してください」と伝え、「このようにAIにアドバイスをもらいながら文章を直していくのもいいのではないかと思います」と結んだ。
もしここで文章の改善案を教師が指摘していたら、児童は評価や指導と受け止めてその通りに修正してしまう可能性が高い。一方、生成AIは教師と違い“誰でもない”存在なので、気兼ねなくそのアドバイスを「退ける」こともできるのがメリットだ。その適度な関係がこの授業にも現れていた。
ちなみに、CopilotはWebの情報を直接参照することもできるが、今回の公開授業は児童のSwayが学内アカウントで作成されていたため、サインインしていないCopilotから参照できない、というシーンもあった。AIに児童生徒の個人情報が勝手に学習されてしまうのでは、という懸念はつきものだが、こうしたアクセスコントロールがしっかりされていることも、教育現場でAIを利用する上で重要な要素だ。
作りながら修正、制作サイクルはAI時代ならでは
この日印象的だったのは、午前の取材から午後の授業にかけてのスピード感だ。児童が取材してきたばかりのメモと写真素材をもとに短時間でレポートの形にしていく姿は、デジタル手段が定着しクラウドによるデータ共有が馴染んでいるからこそ。さらに、完成度は高くなくともレポートを作りながら共有し、その状態で生成AIに改善点を聞いて修正を検討し、完成度を高めていくという制作のサイクルは、AI時代ならではと言えるだろう。
今回の生成AIを使った公開授業について鈴木教諭は、「たとえCopilotがなにか有効なアドバイスを出してきたとしても、児童が必ずしもそれをありがたく受け取るわけではないという姿が見えました」と振り返る。AIが瞬時に出してくる修正案を、児童が言われるがまま採用するのではなく、違和感を表明できるというのは、“自分はこう書きたい”という意志や思いがあるからだ。よく懸念される「生成AIに感想文を書かせて楽をする」というような態度とは全く違う。
また、生成AIの修正案に対して「負けた気がする」という発言があったことについて鈴木教諭は、「負けた気がするというのは、生成AIに勝ちたいという気持ちがあるということですよね」とコメントする。確かに、“生成AIにやらせれば楽ができる”という発想をしていたら出てこない言葉で、児童の主体的な気持ちが見える。
鈴木教諭の学級ではこれまでも、生成AIでできることやその特徴を児童が実感できるような授業を行ってきた。最近では、「生成AIがこんなことまでできるのに、なぜ勉強しなければいけないのか?」という問いを抱えているまっただ中だという。自分の意志の元で生成AIを使うという適度な距離感は、こうした積み重ねで育まれていくのだろう。
AIと共存する時代に児童たちにどのようなAIとの関係を見せ、体験する場を作り、自分の意志で使いこなす側に立つ力をつけるのか、EDIXの場で改めて問いかける機会となった。

















































![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)