トピック
高校の主要5教科で使えるマインクラフト教材「Classcraft」をリリース、高校の学びを本気で楽しくする
プロマインクラフターのタツナミ・シュウイチ氏と教員らが教材開発
- 提供:
- NASEF JAPAN(国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部)
2024年6月27日 06:30
受験勉強や入試対策も大事だけど、高校の授業をもっと変えたい!そんな想いを持っている先生は多いだろう。教えることが多く、授業を変えるのが難しい高校の学習。もっと生徒たちが学びを楽しむことはできないだろうか。
そんな課題を抱える先生に紹介したいのが、マインクラフトを活用した高校向けPBL教材「Classcraft」だ。マインクラフトは今の高校生の多くが小中学校時代に親しんできた人気ゲームで、NASEF JAPANはそのマインクラフトを活用して高校の授業で使えるPBL教材を開発した。同教材の体験授業も行われた、第5回「NASEF JAPAN eスポーツ国際教育サミット」(2024年6月1日開催)の様子をお伝えしよう。
①高校向けの主要5教科で活用できる授業用教材「Classcraft」を開発
②理科編:マイクラの仮想空間で興味を広げた後に、本物を体験する
③英語編:マイクラなら生徒同士のコミュニケーションも創発しやすい
④待ってました!高校向けのマインクラフト教材
⑤高校で進むeスポーツ活用、大学進学からキャリア教育まで
⑥アメリカ本国からも責任者が来日、PBL教育への転換を訴える
高校向けの主要5教科で活用できる授業用教材「Classcraft」を開発
NASEF JAPAN(ナセフ ジャパン/特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク 日本本部)は、2017年にアメリカで設立された教育団体「NASEF」の日本本部で、eスポーツなどのゲームをツールとして、STEAM教育の推進やDX人材・グローバル人材の育成に取り組んでいる。世界70か国で6500以上の団体と提携しており、日本においても高校のパソコン部やeスポーツ部など523校が加盟している(2024年6月1日時点)。
NASEF JAPAN 理事長の松原昭博氏は、「eスポーツはあくまでも教育への入り口のひとつだ」と強調。eスポーツを広げることが目的ではなく、生徒たちの好きなゲームをきっかけに学びへの興味・関心を高め、次世代の人材育成に貢献することがミッションだという。その教育手法として、アメリカで広がっているPBL教育の推進に力を入れていると話す。
同法人のeスポーツ・スカラスティック・ディレクター 坪山義明氏は、ゲームを活用したPBL教育として、マインクラフトが効果的だと述べた。「生徒の創造力や問題解決能力を高められる効果があり、ゲームを通じて生徒が主体的に学び、協力することでリーダシップやチームワークのスキルも養える」とマインクラフトと教育の親和性について語った。
そこで、同法人ではマインクラフトを活用したPBL教材教育・STREAM教育(※)の教材開発プロジェクト「NASEF JAPAN craft Project」を発足。高校向けの主要5教科で活用できる授業用教材「Classcraft」と、総合的な探究の時間や部活動で活用できる教材「Clubcraft」の2カテゴリーで教材開発を手掛けた。これらの教材は、NASEF JAPANの加盟校に無償提供している。
※科学(Science)、技術(Technology)、ロボット工学(Robotics)、工学(Engineering)、芸術・リベラルアーツ(Arts)、数学(Mathematics)の6つの領域を指す。
理科編:マイクラの仮想空間で興味を広げた後に、本物を体験する
今回、新たに発表されたのは「Classcraft」の教材だ。「理科編 化学 炎色反応」「理科編 地学 火成岩」「英語編 異文化理解 ~ゲルを建築しよう!~」の3教材がリリースされた。新高校1年生を対象としているが、学年に関係なく学習内容に興味を持たせるきっかけとして使える。
体験授業では、高校の地学基礎「個体地球とその活動」の単元で活用できる教材「理科編 地学 火成岩」を使って行われた。マインクラフト内で火山を観察して岩石の構成を理解し、本物の岩石との違いを比較するという学習で、授業は2コマとなっている。
教材を開発した理科専科教員の岩田智文教諭は「理科教育においてマインクラフトを活用する最大のメリットは、仮想世界と現実のベストミックスができることだ」と強調する。火山の観察など現実では経験するのが難しいこともマインクラフトの世界でなら体験できる。生徒も興味を持ちやすく、学習のつながりが作りやすいという。
体験授業では、参加者らが基本的な操作を学んだ後、ワールド内に作られた理科室へ移動。これから向かう採掘場で使用する「バケツ」や「カメラ」、採掘した岩石の組成要素を調べる「物質還元器」などの道具を用意し、使い方を確認した。
準備が完了したら、火山付近の採掘場へ! ミッションは、閃緑岩・花崗岩・安山岩といった岩石を採取すること。採掘場では、高い所から落ちないようにバリアブロックで守られているほか、地表に流れる溶岩をバケツですくうなど、現実世界では不可能な体験もできる。
採掘後は、再び理科室へ。採取した岩石を物質還元器の中に入れて分析し、結果を専用のワークシートに記入していく。例えば、「溶岩入りバケツ」を物質還元器に入れると、複数の元素が表示され、さまざまな岩石が混ざって溶岩が形成されていることがわかった。これなら、理科嫌いな生徒や元素記号が苦手な生徒も「ちょっと面白いかも」と興味を持ちやすい。
次は、スマートフォンに装着できるモバイル顕微鏡と本物の岩石がセットになった観察キットが登場。桜島産火山灰を専用の「シャーレ」に入れると、部分的に透明でガラス質の結晶が確認できた。本物の火山灰を観察することでマインクラフトの仮想世界で見た岩石との違いに気づくことができる。そして、なぜ違うのか、その原因を知りたくなるところに学習への意欲を持てそうだ。
岩田教諭はこの教材について、マインクラフトの世界で知識として”知っている”のと、“本物に触れる”ことは大きな違いがあると語る。「本物が目の前にあるからこそ、よく見て観察しようとする。マインクラフトの世界で終わらせず、生徒の物事を捉える視点や思考が育成できるよう、理科の本質を突き詰める観点を忘れないように教材を作成した」と語っている。
英語編: マイクラなら生徒同士のコミュニケーションも創発しやすい
続いては、「英語編 異文化理解 ~ゲルを建築しよう!~」の教材を使った体験授業。英語コミュニケーションⅠの科目で活用できる教材で、テーマは異文化理解。生徒の英語力はCEFR A2以上を想定している。
学習内容は、生徒が2人1組になりマインクラフトの中で「建築士」と「大工」の役割に分かれて、モンゴルの伝統住居であるゲルを建築すること。建築士が完成版のゲルに入り、大工は未完成のゲルに入って、建築士が英語で指示を出す。「5番の位置に青いベッドを置いて」と指示された大工はその通りに置いてゲルの中のインテリアを完成させていく、というのがメインの活動だ。
同教材を開発した中高教員で教育クリエイターの芹澤和彦氏は、「英語のやり取りを活性化させるために、インフォメーション・ギャップを取り入れた」と話す。これは英語教育の手法のひとつで、それぞれが持っている情報のズレを利用して問答を行い、コミュニケーションを活性化させる方法のこと。
「高校生になると英語で積極的に会話をさせるのは難しいが、マインクラフトであれば会話を創発しやすい。今まで教室になかった英語のコミュニケーションが生まれる」と同氏は語っている。
授業は日本語での発話は禁止で、会話は英語のみ。建築に入る前に、会話が活性化するよう、モンゴルの文化やゲルに関する英語の説明文やキーワードとなる単語を読んで事前知識を習得する。
マインクラフトでの制作時間は25分。ときには身振りを交えながら、建築に必要な情報を英語でパートナーに伝え合う。最初は様子見していた参加者だが、次第に「Is there a chair?」「What color is it?」「It's dark brown.」「Like a Chocolate?」と会話が活性化されてきた。
制限時間が過ぎると、答え合わせタイム。お互いの画面を並べて、指示通りに建築できているかを確認する。その際、建築の進み具合や完成度は評価の対象には入らないという。大事なのは英語でコミュニケーションを取ることで、むしろ出来上がったゲルが互いに異なっているほど、会話が盛り上がるというのだ。
後半のプレゼンテーションでは、建築したゲルと日本の住居とを比べて異なる点や気付いたことを英語で発表し、異文化に対する理解を深めた。芹澤氏は、「用意された英文を話すプレゼンテーションではなく、瞬発的に意味のあるやり取りを行う活動なので言語習得に大いに役立つ」と語る。ゲルの建築を完成させるという1つの活動を通して、高校生が活発に英語でやり取りする姿が思い浮かべられる。
待ってました!高校向けのマインクラフト教材
第5回「NASEF JAPAN eスポーツ国際教育サミット」では体験授業のほかに、同教材の開発に関わったプロマインクラフターで東京大学大学院 客員研究員/常葉大学 客員教授 タツナミ シュウイチ氏も登壇した。
同氏は、「高校向けのマインクラフト教材は待ってました!という感じですね」と述べた。「マインクラフトを活用した教材は小学生向けのプログラミング教材が多いが、マインクラフトの中でプログラミングはほんの一部であり、むしろ、学校の学習につながる部分の方が多い。今回のような教科学習に使える教材が開発され、しかも高校向けというのは、『マイクラ×教育』の幅が広がったといえる」(同氏)。
同じく、教材開発に関わった小学校教諭/エデュテイメントプロデューサー 正頭英和氏は、「Classcraftは、マインクラフトを通して英語を学ぶ楽しさをもたらしてくれるはず」と語る。この体験を通して得た”楽しい”という感情が大切で、学びの意欲につながるという。さらに体験には「調べてみる」「作ってみる」「試してみる」という活動が重要で、児童生徒の学びの土台を広げる。「変化が激しく解決すべき問題が多様化する社会では、児童生徒の興味関心・好奇心を育てることが大切、ゲームなどを活用するエデュテインメントはその役割を担う」と正頭氏は語った。
高校で進むeスポーツ活用、大学進学からキャリア教育まで
同サミットでは、NASEF JAPAN加盟校の教員と元文部科学省事務次官 義本博司氏がeスポーツについて語るパネルディスカッションも実施された。
修道中学・高等学校 中学校教頭 藏下一成氏は、「世間の印象では、まだまだeスポーツは競技としてのイメージが強い」と語る。物理班という名称でeスポーツに取り組む同校では、生徒たちがゲームのプレーヤーだけでなく、イベント運営や戦略を考えるストラテジスト、またはチームのPRを担当するコンテンツ制作など、自分の得意分野を生かして様々な役割を分担しているという。藏下氏は「eスポーツを通して国際交流が生まれる機会も増え、語学教育においても良い影響を実感している」と述べた。
立修館高等専修学校 情報教育担当 板垣聡美氏は、eスポーツ特待で大学に進学した生徒も出てきたと語った。同氏は「自分の得意分野を発揮できるのが、eスポーツ部のいいところであり、それが学校でeスポーツを扱う理由だ」と明言。「中学時代に不登校を経験した生徒がeスポーツを通して自信を付け、成長する姿を見ることが教員にとっても幸せなことだ」と語った。
また同校ではマインクラフトを通して県が抱える農業課題の解決に取り組む高校生向けのコンテスト「FARMCRAFT(ファームクラフト)」に参加。それまで農業に関心がなかった生徒が、自分のアイデアを農業協同組合の職員にプレゼンテーションし、学びを深めたエピソードを紹介した。
学校現場での取り組みを受け、義本氏は「eスポーツは生徒と社会をつなげる架け橋であり、PBL教育を進めるうえで大きなツールとなる」と期待を寄せている。「eスポーツを入り口に、生徒が課題に取り組み、PDCAサイクルを回して学びを深める活動は探究学習の狙いと合致しており、行政的として全国に広める意義は大きい」と後押し。「生徒がどれだけ変わったか、世間の人々や教育関係者が理解できる機会を増やすことが大事」だと語った。
アメリカ本国からも責任者が来日、PBL教育への転換を訴える
同イベントには、NASEF最高教育責任者 ケビン・ブラウン氏も登壇しPBL教育への転換を訴えた。「日本同様、アメリカにおいても生徒は教科書から学ぶことが基本であるが、知識伝達型の教育は限界がある。『教える』から『導く』へ、教員の役割を変えていくことが重要だ」と述べた。
具体的には、「生徒が学んだ結果をいかにアウトプットするか」が従来の教育と異なる部分であり、アウトプットの質が深い学びにつながるのだという。さらにブラウン氏は、「失敗を通して学ぶことも重要であり、その体験こそが教科書に載っていない学びを与えてくれる」と強調した。
また、Forsyth Virtual Academy Esports Club に所属し、eスポーツの教育的活用推進に取り組むピーケー・グラフ氏は、「教育は生徒にとってプレイグランド(遊び場)のようなもの」と語った。eスポーツは誰でも簡単に始めることができ、目標を達成する過程で創造性やチームのつながりについて学べる。一方で、安全かつ健康的な取り組み方が重要で、ゲームをプレイする前後やゲームのプレイ中に自分の感情をコントロールすることの大切さを伝えた。
高校の授業でマインクラフトの教材を使う。そんな「遊び」の要素は授業に取り入れらないと思われる先生もいるだろうが、そういう先生にこそ、ぜひ使ってもらいたい。いつも黙っている生徒が積極的に学習に取り組む姿を見れば、マインクラフトの持つ魅力を実感できるだろう。NASEF JAPANでは、11月まで全国の高校でPBL教育教員研修会を実施している。そうした機会を利用して、授業改善のきっかけにしていただきたい。
NASEF JAPAN(国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部)では本部の理念を基にして、eスポーツを通じて次世代日本を担う中高生の健全育成を促進し、デジタル人材の育成に資することを目的としています。













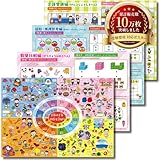











![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)













