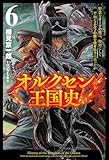レポート
イベント・セミナー
子供のネット利用、親子で話し合って決めたルールは守られやすい
──Innovation Nippon 2025シンポジウムより
2025年7月11日 06:30
スマホやYouTube、SNSなど、子供のネット利用を「なるべく制限したい」と考える保護者は多いが、その一方で、学習や生活にうまく役立ててほしいという思いも少なくない。
安全性への不安が根強い中、広がり続ける子供たちのネット利用にどのように向き合うべきか。これをテーマに研究者や教育者、事業者らが一堂に議論するイベント「Innovation Nippon 2025 シンポジウム 子どもと社会をつなぐ、インターネットの未来像」が、2025年6月26日に開催された。その模様をレポートする。
■国の方針も「利用制限」から「利活用前提」へ
■YouTube、信頼できるものを届け 不適切なものを抑える仕組みを強化
■親子で決めたルールは守られやすい──調査が示す話し合いの重要性
■子供や青少年に関わる関係者が知見を持ち寄ったパネルディスカッション
■関係者の連携による実践的な取り組みが必要
国の方針も「利用制限」から「利活用前提」へ
基調講演には、総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 企画官の吉田弘毅氏が登壇した。同氏によれば、YouTubeやSNS、学習アプリなどのネット利用は、さらに低年齢化・長時間化が進んでおり、9歳時点でのネット利用率は95.2%に達している。青少年の平均ネット利用時間についても約5時間2分に及ぶと資料で示した。
こうした状況を踏まえ、政府は従来から青少年インターネット環境整備法に基づき、特定事業者に対してフィルタリングサービスの提供などを課してきた。しかし、これらの方針は平成21年に策定されたものであり、現在の実態にはそぐわない部分も多い。
そのため数年おきに基本計画が作られており、昨年9月に策定された第6次基本計画では、「利用制限」に重きを置くのではなく、子供たちがリテラシーを高めつつネットを正しく使えるよう「利活用前提」への方針転換が示された。この中では、保護者への働きかけやペアレンタルコントロールの活用、家庭内ルールの確立が重要な柱とされている。
これに対して、総務省は各種ICTリテラシー教材の整備を進めており、全国の学校等で無料講座「e-ネットキャラバン」を展開している。2024年にはこの講座を約44万人が受講したと語った。
YouTube、信頼できるものを届け 不適切なものを抑える仕組みを強化
子供の利用率が特に高いYouTubeについて、グーグル合同会社 YouTube 政府渉外・公共政策部 ジャパン リードの野田由比子氏が登壇し、青少年保護への取り組みを紹介した。
YouTubeでは、2023年10月に運営上の指針として「子どもと青少年に関するYouTubeの基本的な考え方」を発表し、18歳未満のユーザーにパーソナライズ広告を配信していない。また、YouTubeのコミュニティガイドラインを設け、ポリシーに基づいた対処を実施しているという。
さらに「4つの“R”の原則」に基づき、信頼できる情報を届ける仕組みを強化している。専門家の指摘を踏まえ、ポリシーに違反していなくても18歳未満に不適切と判断される動画には年齢制限をかけているほか、身体的特徴の比較や他人への嘲笑、不適切な金融アドバイスに関する動画は繰り返しおすすめしない設計にしている。
【4つの“R”の原則】
・Remove …ポリシー違反のコンテンツを 削除する
・Raise …信頼できる情報を 見つけやすくする
・Reduce …ボーダーライン上のコンテンツの拡散を 減らす
・Reward …信頼できるクリエイターに 還元する
「おすすめ機能」についても専門家の意見をもとに改良しており、関連度や人気度だけでなく、政治・医療・科学情報は信頼性の高い情報源が上位に表示されるとのこと。これにはGoogle検索やGoogleニュースの情報などいくつかのシグナルを用いて信頼性を判断しているという。
2024年9月からは、13歳から17歳の青少年とその保護者が「ファミリーセンター」でアカウントをリンクして、投稿動画やライブ配信、コメント件数などの活動を保護者が確認できる新機能も導入された。
このほか、機械学習を活用してGoogleアカウント利用者の年齢をより正確に把握し、18歳以下と推定される場合には追加の保護を適用する取り組みも進めている。
親子で決めたルールは守られやすい──調査が示す話し合いの重要性
国際大学GLOCOM 准教授・主幹研究員の山口真一氏は、「青少年のインターネット利用に関する調査研究」の結果と、そこから導かれる提言を示した。この調査研究は2025年5月に公開されている。調査は、同じ家庭内の保護者と青少年、合わせて4,800人(各2,400人)を対象に実施したアンケートに基づくものであり、さらに10名の青少年へのヒアリングも行われた。
山口氏によれば、スマートフォン利用の低年齢化が進んでおり、利用サービスでは「動画共有サービス」が87%、「SNS」が70.5%と高い割合を占めた。また、保護者が認識している以上に、青少年は多様なサービスを利用している実態も明らかとなった。青少年はデジタル機器のメリットを「情報収集や共有が簡単で、友人といつでも連絡が取れる利便性」にあると認識しているという。
一方で、トラブルの実態として最も多かったのは「使いすぎによる学業や生活への支障」であり、26.1%と全体の4人に1人が悩んでいることが分かった。青少年自身もこれを深刻な問題と捉えている。また、他人との比較や承認欲求によるストレスが次に多く、これは海外でも大きな課題として認識されている。
偽・誤情報のトラブルも顕著で、実は青少年より保護者の方が2~3倍多く偽情報に接触しており、見抜く力は青少年の方が高い傾向にあるという。ただし、青少年は偽情報を拡散しやすい特徴がある。
山口氏が「特に重要」と強調したのは、ペアレンタルコントロールサービスの活用と家庭内ルールの設定である。調査では、親子で話し合って決めたルールほど守られる傾向にあることが示され、親子の対話の重要性が裏付けられた。
さらに、啓発活動の手段としては「学校での講座」「インターネット上の動画」「学校のチラシ・パンフレット」の需要が高い結果となった。中高生の約3割はネット利用に関する啓発を受けたことがない実態も明らかになっており、学校での啓発の必要性も指摘された。
最後に山口氏は、今回の調査研究から行政には「家庭内ルール作りの支援強化」や「啓発の拡充とポータルサイトの創設」、教育現場には「メディア情報リテラシー教育の拡充」、事業者には「年齢確認の実効性向上」と「子供向けアプリのさらなる開発・実装」を提案した。保護者に対しては、「子供を見守るだけでなく共に育つという視点から、ルールと学びを親子で共有することの重要性」を訴えた。
子供や青少年に関わる関係者が知見を持ち寄ったパネルディスカッション
シンポジウム後半では2回のパネルディスカッションが行われ、教育者や事業者、有識者らが登壇し、現状の課題や役割、連携の必要性について意見を交わした。
LINEヤフーの今子さゆり氏は「信頼できる情報を積極的に発信することが重要」と述べ、Yahoo!ニュースのコメント欄にAIでガイドライン違反を検知し注意を促す仕組みを紹介した。小学館の小林浩一氏は「社会環境の整備も子供の視点を忘れず、説教っぽくならないようエンタメの中に取り入れるなど、ストーリー性を持って伝えていきたい」と述べた。
Adoraの冨田直人氏は、子供にネットやSNSを完全に禁止すると、かえってリテラシーが育たず問題を引き起こすと指摘し、「安心・安全に使えるよう、子供の視点に立ったサービスを提供したい」と述べた。一方、国際大学GLOCOMの渡辺智暁氏は、親と子の望むことには隔たりがあり、大人の価値観はそのまま子供には通用しないと指摘した。例えば、LGBTQなど子供がセンシティブな問題を抱えていた場合、ネットが持つ多様性への接点が失われ、誰にも相談しづらい深刻な問題へと発展する可能性もあると語った。
LINEヤフーの吉田 奨氏(セーファーインターネット協会専務理事)は、削除依頼の判断の難しさや、同協会に寄せられる誹謗中傷相談(昨年186件)について触れ、心身ケアを含む官民連携の課題を語った。朝日学生新聞社の富貴大輔氏は、フェイクニュースに惑わされない力を育むには常識や仕組みへの理解が不可欠だとし、長期的に養うべき力と短期的にすぐ役立つ知識の両面から情報を提供していると述べた。
現役保育士のてぃ先生は、幼児の保護者からスマホやネットの相談が多く、共通点として、動画やネットに触れているときに、子供を1人にしていることを指摘した。「適切に使わせるには大人が翻訳者となり、絵本と同じように大人が楽しみ方を教える必要がある」と語った。LM虎ノ門南法律事務所の上沼紫野氏は、第二東京弁護士会「弁護士子どもSNS相談」に昨年約2700件の相談があり、その11%がネット関連だったと説明。最近は面白半分で転送し「加害者になってしまった」と不安を抱く相談が増えており、「子供は失敗するもの。何とかしてあげたい」と述べた。












































![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)