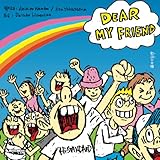ナレッジ
子供たちが「自ら学ぶ力」を発揮できる学校とは
教育学者・汐見稔幸氏の最新刊『学校とは何か 子どもの学びにとって一番大切なこと』刊行
2024年8月28日 12:03
株式会社 河出書房新社は、2024年8月27日に『学校とは何か 子どもの学びにとって一番大切なこと』を発売した。
編著者の汐見稔幸氏は、全国の幼稚園や小学校、中学校、高等学校などで講演を行う教育学者である。汐見氏は、教育の原理を「教え方」から「学び方」へと転換することを提唱し、その考えを2021年に刊行された『教えから学びへ』で詳述した。
今回の新刊『学校とは何か 子どもの学びにとって一番大切なこと』では、教育現場での具体的な実践事例を通して、「教え」の教育から「学びを支える」教育への転換を提唱している。具体的には、教育改革を進めるために、学校全体で子供の学びに寄り添いながら少しずつ変化を進めることが必要という。
同書では、教育ライターの太田美由紀氏による取材記事を掲載。改革を進める学校での生徒たちの生き生きとした姿を取り上げ、教員や保護者の価値観がどのように変わり、学びに対するどのような視点が得られたかをレポートしている。
例えば、神奈川県大和市立下福田中学校では、週に1回「探究」の授業を導入し、生徒たちが自らの興味に基づいて学びを深めている。また、東京都新宿区立柏木小学校では、試行錯誤しながら児童生徒が自分に合った学び方を選び、全国の教育現場から注目を集めているという。
各章末には、汐見氏による「教えから学びにふみ出すために」と題したコラムを掲載。具体的な事例を参考にしながら、子供たちの「学び」を変えるためのヒントを提供する。
目次
はじめに いま、学校が変わりはじめている
第1章 「学び」のスイッチを入れる──できる・できないからの解放
・神奈川県大和市立下福田中学校
・神奈川県大和市立引地台中学校分教室
第2章 「学び」に向かう前提──主体的な学び・個別最適化
・東京都品川区立清水台小学校昭和大学病院院内さいかち学級
・埼玉県さいたま市立桜木小学校
第3章 自分に合う「学び」方──一斉授業からの脱却
・神奈川県横浜市公立小学校
・東京都新宿区立柏木小学校
第4章 正解のない「学び」──プロジェクト学習・縦割り
・新潟県長岡市立表町小学校
・学校法人きのくに子どもの村学園 南アルプス子どもの村小学校
第5章 多様な子どもたちが安心して学べる環境──インクルーシブ教育を目指して
・京都府八幡市立中央小学校
・東京都狛江市立狛江第三小学校
第6章 教員の視点の転換のために──教育委員会の動き
・豊岡市教育委員会(兵庫県)
・広島県教育委員会
取材後記(太田美由紀)
おわりに
編著者
汐見稔幸(しおみ・としゆき)
1947年、大阪府生まれ。専門は、幼児・児童教育学、保育学、教育学。東京大学名誉教授。白梅学園大学名誉学長。著書に『教えから学びへ 教育にとって一番大切なこと』(河出新書)、『本当は怖い小学一年生』『「天才」は学校で育たない』(ともにポプラ新書)、『人生を豊かにする学び方』(ちくまプリマー新書)など。
書誌情報
書名:『学校とは何か 子どもの学びにとって一番大切なこと』
著者:汐見稔幸 編著
発売日:2024年8月27日
定価:1,100円(本体1,000円+税10%)
仕様:新書判
ページ数:368ページ
ISBN:9784309631769
発行:株式会社 河出書房新社






























![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)