トピック
生成AIは思考の伴走者、探究学習を切り拓く若狭高校の現場から
――【後編】福井県立若狭高等学校・渡邉久暢氏インタビュー
- 提供:
- 日本マイクロソフト株式会社
2025年9月17日 06:40
前編 では、福井県立若狭高校の教育理念と生成AIを活用する意義、そして学びにもたらす変容について、渡邉久暢校長に考えを伺った。後編では、さらに一歩踏み込み、授業デザインや生成AIを活用する際の注意点、教師のマインドについて語っていただく。
生成AIは思考の伴走者 答えの供給装置にしない授業デザインを
──生徒がCopilotを使うときは、どのように導入し、どのように活用するのが有意義でしょうか。また、気を付けるべき点があればお聞かせください。
Copilotの活用について、教師と児童生徒でまったく別のものとして扱う必要はないと考えています。実際には、似たような使い方をする場面も多く、根底にある利用の本質は共通しているからです。
とはいえ、生徒の発達段階に応じた注意は欠かせません。たとえば、Copilotが返す答えをそのままコピー&ペーストしてしまったり、AIに過度に依存して自分で考えるプロセスを飛ばしてしまったりすることも想定されます。こうしたリスクを踏まえたうえで、Copilotを導入する際には、 単なる「情報の供給装置」としてではなく、「思考の伴走者」として捉えさせるような授業デザインが重要 です。
もし、生成AIを「便利な答え製造機」のように扱ってしまえば、学習は「ただ真似て終わり」「答えをもらって終わり」という受け身な活動になってしまいます。こうした誤解は、大人自身が生成AIを「すぐに答えが返ってくる便利ツール」と捉えていることにも原因があるのかもしれません。
だからこそ、社会的に生成AIの活用価値やリスクがまだ定まりきっていない今こそ、学校という安心・安全な環境で、生徒自身が試行錯誤しながら体験することが大切です。教師が見守る場だからこそ、挑戦や失敗を通じて学ぶことができます。もし学校でこうした機会を設けなければ、子どもたちは大人の目の届かないところで誤った使い方を覚えてしまうかもしれません。
たとえば、小中学生には、Copilotを「友達のような存在」として紹介するのも有効です。「その友達は完璧ではないし、ときどき間違えることもある。でもあなたに“問い”を投げかけてくれる、一緒に考える相手なんだよ」と伝えれば、AIとの関係性の方向性がより良いものになるでしょう。
とはいえ、「Copilotとはこういうものだ」と断言するのは難しいのが現状です。むしろ今後、生徒たちは「AIエージェント(※)」として役割をもたせた複数の生成AIを状況に応じて使い分けるようになるかもしれません。そうなれば、AIの“見え方”も大きく変化していくはずです。
※AIエージェント:人間のように考えたり判断したりしながら、特定の目的に沿って自律的に行動するAI(人工知能)のこと
また、高校生であっても、1年生と2・3年生では言語能力や抽象的思考のレベルに差があります。同じCopilotを使うにしても、導入の仕方や期待される活用のあり方は学年によって変える必要があるでしょう。
つまり、生成AIの教育活用において大切なのは、 ツールの一律導入ではなく、生徒の発達段階や学習のねらいに応じて、どのように意味づけ、どのように関係づけるか。 その設計と対話の工夫こそが、教師に求められているのだと思います。
生成AIの活用は学習観・指導観を変えていくチャンス
──若狭高校では、2025年度からCopilotの活用をスタートされました。まだ初期段階ということですが、今はどのように進められていますか?
本校は比較的若い教員が多く、私自身を含めて、Copilotの活用には全体として前向きな空気があります。現在は、Copilotに加え、AIドリルや学習支援ソフトなども導入しながら、まずはアプリケーションレベルでの試行的な活用を進めている段階です。
一方で、Copilotを学校全体で一斉に導入するような「トップダウン型」の方針は採っていません。たとえば業務改善の観点から、「一度使ってみてはどうか」と促すことはありますが、基本的には各教員の自発的な判断に委ね、体感を伴った活用を大切にしています。
とくにICTに関しては、無理に統一的な運用を求めるよりも、「使ってみてよかった」と感じた事例を現場で自然に共有し合う文化を育てる方が、結果として定着しやすいと考えています。そうしたボトムアップの取り組みが、若狭高校らしい柔軟で前向きな雰囲気につながっているのではないでしょうか。
──先生方はCopilotの活用にもポジティブですが、そもそも若狭高校は、海洋科学科の宇宙日本食のサバ缶を始め、探究やユニークな取り組みで全国的に知られています。こうしたポジティブで創造性の高い校風は、どのように作り上げられたものなのでしょうか。
私は1991年、母校である若狭高校に初任者として赴任して以来、通算で26年間この学校に関わってきました。その経験から感じるのは、本校にはもともと、地域や企業、大学など外部と積極的に連携し、外の力を取り込もうとする 開かれた校風 が根付いているということです。
また、課題研究や探究活動においても、単発の取り組みではなく「 学校文化 」として長年積み上げてきた基盤があります。たとえば、海洋科学科の「宇宙日本食のサバ缶」プロジェクトは、前身である小浜水産高校時代からの研究を、SSH校としての若狭高校が継承・発展させてきた成果の一つです。この取り組みも、生徒が自ら目標を掲げ、それを教員が尊重しながら見守る――そうした生徒主体の文化の中から生まれたものであり、そこに共感して遠方から入学してくる生徒も少なくありません。
2025年度に私が校長として再び若狭高校に戻ってきてからは、そうした土壌をさらに広げるために、自らが外部との連携窓口となり、地域・企業・大学と新たな関係を築くことを意識してきました。そうして得たネットワークや機会を、 生徒や教職員の学びに還元していくこと が、私の役割だと考えています。
校内にはすでに、「挑戦することをポジティブに捉え、自ら動き出す」空気があり、それを絶やさず育て続けるためには、 外に開かれた実践の場と、内発的な挑戦を育む文化 の両方が必要です。そのバランスを大切にしながら、若狭高校らしい創造的な学びの文化をさらに深めていきたいと考えています。
──学校全体のオープンな文化や先生方の意識やマインドセットに学びをよくしていこうという成長志向を感じます。Copilotを学びに生かすためには、どのようなマインドセットが必要だと思われますか。
私がCopilotの導入に違和感を覚えなかったのは、おそらく私自身が、もともと一斉授業に強く依存しない授業スタイルをとってきたからだと思います。私にとって大切なのは、「どのような方法を使うか(How)」ではなく、「 どのようなことに価値を置き、大切に思うのか(View) 」のほうです。たとえ使うのがCopilotであっても、生徒の学びが深まり、個別に最適化されていくのであれば、教師としての関わり方を変えることに何の抵抗もありません。むしろ、それによって授業がより豊かになるなら積極的に取り入れたいと感じています。
とはいえ、生成AIがもたらす変化は、単なるツールの導入にとどまらず、私たち教師の授業観や学習観、さらには教育観そのものに再考を迫るものでもあります。それゆえに、「自分のやってきたことが通用しなくなるのではないか」という不安や違和感を覚える方がいて当然です。生成AIの登場は、教師にとって“アイデンティティの問い直し”にもつながるのですから。
だからこそ私は、「怖い」と感じる気持ちもとてもよくわかります。しかし、今この段階で生成AIを使わないままでいることのほうが、むしろ危ういと感じています。なぜなら、生徒たちはいずれ、生成AIが当たり前に使われる社会の中で生き、働いていくからです。そうであれば、学校という安全な場で、教師の見守りのもと、Copilotを使って試行錯誤しながら学んでいくことが、 本当の意味でのデジタル・シティズンシップ教育 なのではないでしょうか。
そして、私が何より強く感じているのは、生成AIをきっかけにして、これまでの「教師はこうあるべき」「授業とはこういうものだ」といった既成概念を見直すチャンスが訪れているということです。AIが主役になるのではありません。 教師がどのようにAIを活かし、どのような学びの場を構想するか にこそ、教育の未来はかかっているのだと思います。
生成AIという新しい道具を通して、私たち教師自身が「問い直し」を実践し、自らの教育観や授業観を深めていく。そんなプロセスが、これからの教育において本当に大切にされていくことを、私は心から願っています。
▶ 教職員研修の資料として
▶ 校内での共有・実践のヒントに
▶ 教育改革を進めるための議論の土台に
生成AIの価値を再発見し、同僚性と探究の広がりを生むヒントとして、ぜひご活用ください。📥 無料冊子をダウンロードする




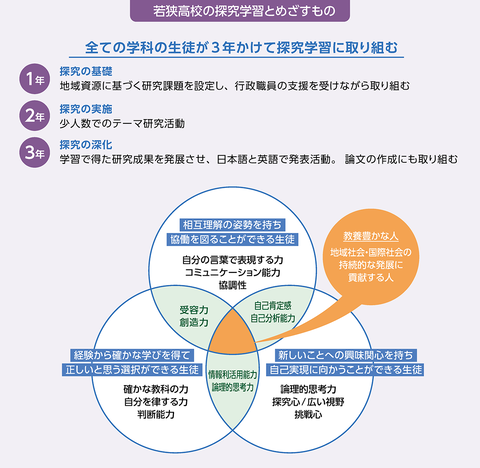

























![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)














