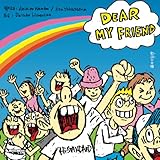コラム
何のためのICT活用なのか、目指す教育は何か―主体的な学びをつくるために、学校や教員に求められている変化
~『実践例&導入事例でわかる 明日からの教室のつくりかた スクールタクトで始めるICT活用』より
2023年7月5日 12:05
本稿は、2023年7月5日発売の書籍『実践例&導入事例でわかる 明日からの教室のつくりかた スクールタクトで始めるICT活用』(インプレス)第3章鼎談1より冒頭を抜粋してお届けします。
ICT活用によって学びが良くなるとはどういうことか。押さえておきたい大切なこととは?
─ GIGAスクール構想から3年が過ぎ、学校現場におけるICT活用も広がってきました。現状をどのように見ているのか、また全体的にICT活用を通して学びは良くなっているのでしょうか。
後藤: 僕はGIGAスクール構想のような大きな変化は、もっと後に来ると思っていたのですが、それが2020年代に起きたことはうれしい変化でした。これでようやく学びのあり方が変わるきっかけができたなと。
スクールタクトの活用でいうと、GIGAスクール構想以降、使ってくださる方がかなり増えましたね。使う場面も一斉授業だけでなく、探究学習や協働学習など多様な使い方が増えてきました。
スクールタクトの一番の特徴である、リアルタイムに児童生徒の状況が分かるという良さを理解してくださる方が増え、「これなら児童生徒同士で学び合いができるかもしれない」と思っていただいているようです。こうした教員の気付きが児童生徒主体の授業に変わっていくきっかけになっているのではないかと思っています。
苫野: スクールタクト、私も授業で使っています。
大学の授業では、前半では教育の哲学的な本質から最新情報まで、知識・情報のシャワーを学生たちには浴びてもらっています。大量の本を読んだり、動画を見たりして、学生たちは考えたことなどをスクールタクトに書き出していくんです。それをみんなで読み合って、対話やディスカッションをしたりしています。
後半は、前半で学び取ったことをベースに、チームや個人でさまざまなプロジェクトに取り組んでいきます。自分たちでテーマや問いを立て、文献を読むのはもちろん、全国の素晴らしい実践をされている学校に視察に行ったり、先生方などにインタビューをしたりして。120人くらい学生がいますが、お互いのプロジェクトの進捗具合をシェアするときにも、スクールタクトはすごく役に立ちました。探究学習には、とても使いやすいツールだと思っています。
後藤: ありがとうございます。似たような使い方として、愛知県岡崎市でも4人で1チームを作り、学び合いができているかどうかをお互いに確認しながら学習されている事例があります。
一般的にチームで学習を行う場合、教室で4人が席を移動して1つのチームになることがこれまでのやり方だと思いますが、スクールタクトなら誰がどこの席にいても、もっといえば空間すら違っても、児童生徒は学び合いができますよね。お互いの考え方を共有することによって学び合う、こういう学びができるようになってきたのは良い方向だと思います。
山口: そうですね、私もGIGAスクール構想でICT活用が進んだことは良かったと思います。でも、これからは、学びの質に特にこだわっていきたいですね。
例えば、学びの個別化。ICTは、児童生徒一人一人に自分の興味や関心、得意を生かし苦手を補うような学び方をこれまで以上に選択可能にするわけですが、そもそも、その選択の機会を教員は十分に与えているでしょうか。教員が指示した通りの方法やペースで学ばなければならないとしたら、そのことでみんなと共に学び成長する機会を逸してしまう児童生徒はたくさんいます。
けれど、もう一方では、教員の労力や負担もしっかり考えなければならないですよね。個別化した全員の学習状況をどう見取るのか、一人一人に合わせた支援や指導をどう行うのか。今の例は学びの方法面の話ですが、学びの内容面も含めてその質にこだわりつつ、児童生徒と教員の両方の視点からICTの活用を考えることが大事だなと思います。
苫野: おっしゃる通りですね。哲学者の立場からいえば、どんな学びのあり方も、そもそも何のために学校教育があるのかをベースに考えなければなりません。
それは「みんなが自由に生きるために、つまり生きたいように生きられる力を確実に育むため」です。それから同時に、「自由の相互承認(※1)の感度を育むため」でもあります。また、公教育の政策は「一般福祉」にかなうものでなければ正当性を持ちません。つまり、「自由」「自由の相互承認」「一般福祉」という3つの大きな原理があるわけです。
※1 「すべての人が対等に自由な存在であることをお互いに認め合う。そのことをルールにした社会」という考え。哲学者の竹田青嗣がヘーゲルの「相互承認」の原理を表現し直したもの。
これら3つの原理をベースに、私たちは、どのような学びのあり方が良いのか、その際に必要なツールは何か、といったことを考えていく必要があります。この構造を、私たちは決して見失ってはいけません。ICTやテクノロジーの進化によって、「こんなことができるようになったから、こんな学びもできるかもしれない」という考え方も重要ですが、そのときも、それは一体何のためか、本当に「良い」といえるのか、という哲学原理を、必ず底に敷いておく必要があるんですね。
私自身は、「自由」「自由の相互承認」「一般福祉」のためには、「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合」へと「学びの構造転換」をしていく必要があるとずっといってきました。ICTは、そのための強力なツールになると考えています。
後藤: そうですね。何のためにICTを活用するのか、どのような学びを目指してICTを活用するのか、それを考えるのがとても重要だと思います。今回、僕が苫野先生と山口さんにお話を聞きたかったのは、そういう部分を深めたかったという意図もあって。
僕はスクールタクトという「方法」を提供する立場ですが、苫野先生の専門である「教育哲学」と山口さんが教育委員会で実践されてきた「理論」を聞くことで、良い学びをつくるためにできることを考えていきたいと思っています。
教育の変化に戸惑う学校現場少しずつの経験で、やっと大きな一歩が踏み出せる
山口: 私の肌感覚なので一般化には留保が必要ですが、学校現場を見ていると、教育やそれを取り巻く環境の変化に大きく戸惑っている教員の中には、実は、私たちと同世代の30代後半から40代の人が結構いるなという気がしています。
もちろん、年配の教員も不慣れさが障壁になることはありますが、そこさえ越えてしまえば学びの質をしっかり考えてICTを活用している人も多い。若手は経験の不足がいい方向に影響することもあって、自由と自由の相互承認の実質化に不可欠な児童生徒が自分で・自分たちで学ぶ学習者主体の授業への転換なども、結構すんなりいくことが多いな、と。そういう全体感の中で、ということです。
後藤: 確かに、ICTを使わない教員は年配の方が多いように思っていましたが、必ずしもそうではないんですね。
山口: 私は、よく「学習者主体と教員の後追いはワンセット」だといっています。学びの質を確保するためには、児童生徒の自分なり・自分たちなりの学びを後から追うように支えたり共に考えたりする必要があって、それが「後伸び」にもつながる。教員の大事な役割です。
でも、アンラーニング(※2)はなかなか難しくて、自分が小・中学生などのときも教員になった後も「教員主体で一斉・一律に確実に教えきる」というような環境で育った人は、それ以外の選択肢があることすら知らない人もいる。だから、児童生徒を先に立たせることが難しいんですよね。不安や怖さも相まって。
※2 これまでの価値観や知識を見直し、新しいものを取り入れること。
苫野: 「信頼して、任せて、待って、支える」。これが教育の基本中の基本だといつもいっていますが、カリキュラムも時間割もあらかじめ決められている今の学校では、その基本を大事にするのがなかなか難しいんですよね。「教員が主体になって確実に教えきる」スタイルが、今のシステムにはどうしても親和的になってしまう。
山口: 私の経験だと、こうした教員が一歩を踏み出すために大事なことは、やっぱり、自分で体験してみることなんですよね。実感を伴って「できるかもしれない」と思えないと、なかなか進めない。
もちろん、原理や理論を知って「ICTはこう使うべきだ」と道筋を立てて自分の実践を変えられる人もいますし、多くの授業事例を見ることで「自分にもできるかもしれない」と始める人もいます。ただ、それがマジョリティーではない。特に学習者主体の学びは、自分でおっかなびっくりやってみて、「意外と手を離しても大丈夫」という経験を少しずつ重ねて、やっと、大きな一歩が踏み出せるようになる人が多いかな、と。
ちなみに、日常を変える必然性や困り感の低さも一因にはなるはずで、極端にいえば、自分の授業で指示が全く通らない、とか、全く統率が取れない、とか、そういう状況にならないと、どうしても忙しさが先行してしまって、じっくり指導や学びの質について振り返る機会を持ちにくいこともあるかなと思います。
苫野: 私のゼミの卒業生ですが、今は熊本市で「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合」を実践している小学校の教員がいます。ゼミ生とは、毎年、イエナプラン(※3)など国内外の実践を視察に行っているのですが、彼はそのときに、「見ちゃった、知っちゃった」という名言を残しました。見てしまった、知ってしまった、できると分かってしまった。そうである以上、もう元には戻れないと。
ただ、彼の場合は多くの実践事例を見ることでその確信を得ることができたわけですが、今、山口さんがいわれたように、ただ見るだけでは一歩を踏み出せないことが多いのも事実です。あと、イエナプランにせよ自由進度学習(※4)にせよ、実際に見ても、そこで何が起こっているのか理解できないという場合も多いです。ある程度の知識やリテラシーを得てからでないと、見ても良さが分からないことがあるんですよね。
※3 ドイツ生まれオランダ育ちといわれる教育で、異年齢のグループでクラスを編成し、一人一人を尊重しながら自律と共生を育む教育。
※4 授業の進度を子供が自ら自由に決めることができる学習法。
山口: 全くそうですね。知識がないと見方が働かない、つまり、「見えない」。そういう意味で教職課程はやはり大事ですよね。
そこで、オルタナティブな学びや教育のあり方、可能性、選択肢があることを知るのと知らないのでは、後が大違い。自分の原体験だけで教員になり、そこから15年、20年とそのまま過ごしてしまうのは、ある意味、とても不幸だなと思います。
後藤: 例えば大正自由教育(※5)とか、戦後の生活単元学習(※6)とか、教育の歴史を勉強していると「それ、ICTがある今だったらもっと良くなるよね」という気付きがありそうですけどね。
大正自由教育、戦後の新教育、平成の個性伸長(※7)と数えると、2017年告示の学習指導要領は、単純労働者の育成と国民の形成を一斉・一律に図ろうと始まった近代の学校教育制度に対する四度目の大きな挑戦になります。今回は、結構、大きく変化するのではないかという期待を持っています。
※5 大正期において欧米で活発化していた新教育が日本にも輸入された。それまでの画一的な教育スタイルから、子供の関心や感動を中心に、より自由で生き生きとした教育体験の創造を目指した教育。
※6 第二次世界大戦に敗北した日本がアメリカによる「日本の学校教育の民主化」の方針を受け採用した教育方法。児童生徒の生活経験によって基礎づけたひとまとまりの学習活動。
※7 平成時代に重視された、自分の良さを生かし、自分らしさを発揮しながら調和な理解のとれた自己を形成していく教育。
苫野: そのために何より大事なことは、やはり「何のための教育か」「何のための学校か」という哲学的な本質論を必ず底に敷くことです。
これまでの3回の改革の試みは、結局、その本質に十分立ち戻れなかった問題があったと私は考えています。大正自由教育は、それまでの公教育へのアンチテーゼという側面が強かったですし、戦後の教育改革も、軍国主義教育へのアンチテーゼという面が強かった。だから種々のゆり戻しがあった。平成になって「総合的な学習の時間」などが始まっていくのも、やはり時代の流れによるところが大きかった。
もちろん、いずれの改革においても本質を考えた人たちはたくさんいたけれど、最後の最後、時代の流れの中で翻弄されてしまったという面がやはり強かった。だからこそ今回は、「何のための教育か」を何よりも大事にし、そこから議論を積み上げていく必要がある。そうじゃないと、結局、はやりで終わってしまいます。
本稿の続きは、以下の書籍でお読みいただけます。


























![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)