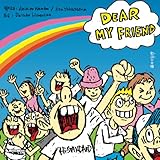【連載】EducAItion Times
「書くのが苦手」な先生へ 生成AIができること、先生にしかできないこと
2025年7月4日 06:30
学級通信、通知表、報告書……。先生の仕事には「書く」仕事が多いですが、しんどいと感じることも少なくないのではないでしょうか。
私はライターや社内広報の仕事をしており、社内外の知人から「どうすればうまく書けるのか?」と相談を受けることが多々あります。どんな仕事でも意外と「書く」機会は多いからこそ、「書く」という行為に苦手意識がある人は多いなと感じています。先生方も、その代表的な例かもしれません。
生成AIにある程度「書く」ことを任せることができる今だからこそ、先生は「書く」という行為のどの部分を担えばいいのか。学級通信を例に考えてみます。
「書く」ものには2種類ある
学級通信には、大きく分けて2種類の性質があります。この2つが混ざっているからややこしいのです。
【① 客観的な「情報」を伝える】これは、 生成AIがとても得意な領域 です。
日時・伝えたい内容などの概要を生成AIに入力して、「学級通信に貼り付けられるように、小見出しをつけて情報を分かりやすく整理してください」とお願いするだけで作れます。学級通信の中に「お知らせ」のようなコーナーを作って、まとめておくと分かりやすいです。
【②あなただけの「視点」を伝える】こそ、 人間にしかできない ことです。
生成AIは、ネットにある情報はすべて取り込むことができます。しかし、あなたの学年・クラスの様子は絶対に分かりません。先生ひとりひとりの、そのクラスを見つめる独特の視点。それは生成AIには絶対に代替できない、あなただけの価値ではないでしょうか。
なぜ「視点」が重要なのか?
②の性質の文章を書く時は、必ず 読み手を意識 します。今回の読み手は、主に保護者の方です。保護者は普段の学校の様子が分からない。我が子がどんな環境で、どんな友達と、どんな風に過ごしているのか。
風土・文化というものは目に見えにくいものです。「クラスの雰囲気は?」と聞かれて、あなたはどう答えますか?
「明るいクラスです」 「みんな仲良しです」 「頑張り屋が多いです」
これらの言葉は間違いではありませんが、保護者には何も伝わりません。抽象的すぎるからです。
そのために、まずは先生である「あなた」が具体的に言葉にしてみる。文章作成は生成AIがやってくれるので、 観察と言語化 に力を入れることができます。
「書くのが苦手」の正体を探ってみよう
「書くのが苦手」と感じる理由は、実は3つの段階が混ざっているからかもしれません。
①何を書くか分からない (ネタ・素材不足)
②どう組み立てればいいか分からない (構成・段取り)
③うまい文章にできない (表現・ライティング)
この中で、②と③は生成AIが大いに手助けしてくれます。つまり、あなたが本当に集中すべきは1番目。「今日、何が起こったか」「何を感じたか」を丁寧に拾い上げることなのです。
これを料理に例えてみましょう。「書く」作業は料理と似ています。
①食材を集める: 新鮮な素材(あなたの体験・観察)を用意
②レシピを考える: どう調理するか構成を決める
③実際に調理する: 文章として仕上げる
生成AIは②と③が得意です。でも①の「新鮮な食材」は、あなたにしか集められません。教室で起こる生の出来事、生徒たちの表情の変化、あなたが感じた空気感。それらは、どんなに優秀な生成AIでも体験できないのです。
先生の「視点」をどう捉えるか?
では具体的に、何を観察し、何を素材として集めればいいのでしょうか?具体的に 5つの観察ポイント を紹介します。ただ、大切なことは、 自分がどう思ったかを大事にする ことです。
「こうあるべき」「こう書かなければ」ではなく、「私はどう感じたか」を大切にしてください。
②比較からの気づき:4月と今の変化/昨年の同学年との違い/他のクラスとの雰囲気の違い
③感情が動いた瞬間:思わず「あっ!」と声が出そうになった場面/胸がキュンとした瞬間/「やられた」と感心した場面/ほっこりした温かい気持ちになった時
④音や声の変化:教室の「静けさ」の質が変わった/笑い声のトーンが明るくなった/「ありがとう」が自然に聞こえるようになった/ざわめきの中にも集中があった
⑤小さな「初めて」:初めて手を挙げた子/初めて自分から話しかけた場面/初めて「分からない」と言えた瞬間/初めてクラス全体が一つになった感覚
また別の方法として、 職員室や友人との会話を思い出してみる のも良いでしょう。親しい友人や同僚に「今日どうだった?」と聞かれて答えるような、率直な感想を思い浮かべてみてください。
例えば、「今日の6時間目、すごかったんだよ。普段全然発言しない子が突然手を挙げて、しかもすごくいいこと言うの。周りもみんな『おお!』って感じで聞き入っちゃって。あの瞬間、教室の空気が変わったのがわかったな」
この 「率直な感想」こそが、あなたにしか見えない「視点」 です。
実際に生成AIをどう利用するか?
利用する生成AIは何でもいいですが、現在は 文章出力に強みのあるClaude がおすすめです。
コピペで使える!プロンプトフォーマット
下記のプロンプトをコピペして、生成AIで文章を作ってみましょう。
【条件】
・分かりやすい見出しタイトルをつける
・個人情報に配慮し、読み手の誰かを傷つけるような表現は避ける
・ポジティブな言い回しに変換する
・保護者が読んで我が子の成長を感じられるように
・●年●組の担任として、親しみやすい文体で
【あなたが感じたこと・観察したこと】
XX(出来事やエピソードを具体的に)
【印象的だった情景・雰囲気】
XX(教室の様子、季節感、時間帯など)
【感情が動いた瞬間】
XX(驚き、感動、発見など、あなたの率直な気持ち)
【音や声の変化】
XX(教室の静けさ、笑い声、会話の様子など)
【小さな「初めて」や変化】
XX(生徒の新しい一面、クラスの成長など)
【比較・時系列での気づき】
XX(4月と比べて、他のクラスと比べて、昨年と比べてなど)
【職員室や友人に話すとしたら】
XX(「今日すごかったんだよ、○○で...」のような自然な語りかけで)
使い方は簡単。●●の部分(文字数、学年組)を埋めて、XXの部分に観察したことを自由に書き込むだけです。全部埋める必要はなく、印象的だった項目だけでもOK。
文化祭準備で、普段静かな生徒が「僕、絵が得意だから描きます」と自分から申し出た。その絵が予想以上に上手で、クラス全体が盛り上がった。
【印象的だった情景・雰囲気】
放課後の教室、夕日が差し込んで暖かい雰囲気。みんなで作業している一体感があった。
【感情が動いた瞬間】
その生徒の絵を見てクラス全体が「すげー!」と声を上げた瞬間。本人の表情が一気に明るくなった。
【職員室や友人に話すとしたら】
「今日すごかったんだよ。普段しゃべらない子が突然『絵描きます』って言い出して、それがまた上手で。みんな『すげー!』って盛り上がって、本人も嬉しそうで...あの瞬間、クラスの空気が変わったのを感じたな」
今日の文化祭準備での出来事に、思わず胸が熱くなりました。普段は控えめな生徒が「僕、絵が得意だから描きます」と自ら手を挙げたのです。正直、どんな絵を描くのか少し心配でしたが、その心配は一瞬で吹き飛びました。
その生徒が描き始めた絵は、私たちの想像をはるかに超える素晴らしいものでした。夕日が差し込む教室で、クラスメイトたちが次々とその生徒の周りに集まり、自然と「すごい!」「かっこいい!」の声が上がります。本人の照れたような、でも嬉しそうな表情を見ていると、「ああ、これがクラスっていうものなんだな」と実感しました。
4月の頃は、まだお互いを知らず、遠慮がちだった生徒たち。それが今では、素直に相手の良さを認め合い、支え合える関係になっています。一人ひとりの中に眠っている可能性を、みんなで見つけ、育て合っているのです。
生成AIで文章作成、使用時の注意点は?
もちろんこのまま使うわけではなく、以下の点は必ずチェックしてください。
ハルシネーション(誤情報)のチェック : 生成AIが事実と異なる内容を作り出していないか確認しましょう。
個人情報・プライバシーの配慮 : 個人を特定できる情報や、誰かを傷つける可能性のある表現がないかチェックしてください。
例えば、上記の「僕、絵が得意だから描きます」というエピソードを取り上げることは、一般的には問題ありません。しかし、もしこの発言をした生徒が感受性の高い子だったり、万が一誰かに無理やり言わされていたりした場合、よかれと思って取り上げたエピソードが、かえって生徒を傷つける可能性もあります。
ここも先生の観察力によるところですが、書かれた生徒がどう受け取るかを想像してみることが大切です。また、直接聞ける関係性があれば「私はこう受け取って、こう表現してみたけれど、あなたの受け取り方と違いはない?この内容で掲載しても大丈夫?」と確認してみてもよいでしょう。お互いの視点を確認すること自体が、対話のきっかけにもなります。
「自分らしい」表現かどうか 「私はこんな言葉遣いするだろうか?」「この表現は、本当に私の言いたいことを伝えているだろうか?」 を必ず確認してください。
例えば、一人ひとりの個性をとても大事にしている優しい先生が、普段は「生徒の"できる"を大事にしています」と言っているのに、生成AIの出力では「個性を尊重した教育方針です」という固い言葉になってしまうことがあります。あなたらしい表現に調整することが大切です。
生成AI活用で変わること
ライターとしての経験から言うと、生成AIを使うことで「①客観的な『情報』を伝える」記事は劇的に書く時間が減りました。
ところが「②あなただけの『視点』を伝える」ような記事は、トータルでそこまで書く時間が変わっていません。でも クオリティは確実によくなっている と感じます。文章にする時間が減った分、 観察・構成の検討により多くの時間をかけられる からです。推敲する回数も増えました。
「先生」という仕事は責任も重く、だからこそ「〜こうあるべき」という思いが自然と強くなる場面が多いのではないかと察しています。長年培われた「先生」という役割を脇に置くのは容易ではなく、「あなたはどう思いますか?」と問われると、少し戸惑われることもあるかもしれません。
それでも少しずつ、「自分はどう感じたか」という視点を大切に、毎月、毎年、担当する生徒たちを見つめていただきたいと思います。そして「書く」ことで言語にし、記録として残す。その積み重ねが観察力や感受性をさらに磨き、クラスの小さな変化にいち早く気づくことにもつながっていくはずです。
生成AIを活用することで、先生方がより豊かな「視点」を育み、それを生徒や保護者たちと共有できる一助になるでしょう。技術はあくまで手段であり、最終的に大切なのは、先生方の目に映る生徒たちの成長と、それを言葉にして伝えていくことではないでしょうか。
私はそれこそが「書く」楽しさだと思っています。
教育や育児に役立つ生成AIの情報や活用方法をお届けするお勧め連載!過去の好評記事もあわせてチェックしてみてください。
▶ バックナンバーはこちらから











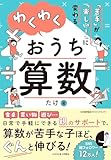

















![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)