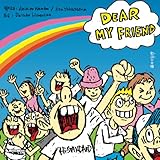レポート
製品・サービス
「学校のプリント、どこ行った?」をなくしたい、ITで乗り切る6人家族の予定管理
2025年7月4日 07:00
どの家庭でも、一度は、学校からの配布物の管理に頭を悩ませた経験があるのではないでしょうか。4人の子供がいる我が家では、子供たちが通う高校や中学からお知らせがほぼ毎日、メールやプリントで続々と届きます。そして、このプリント類の扱いは、家庭内で混乱を招くことも。そんな事態を回避するため、ITを日常に取り入れ奮闘する、6人家族の我が家の取り組みを紹介します。
■家族間の情報共有、気づけば「言った」「言わない」のバトルへ
■【解決策①】プリントのデータ化、紛失しても印刷して提出できる
■【解決策②】iPhoneでデータ化を簡単に、ファミリー共有をフル活用!
■【解決策③】カレンダーアプリで家族の予定管理、カオスな状態を回避!
■【発展編】スマートスピーカーで予定管理、話しかけて予定を登録
■【課題と期待】スマートだけど抜けてるところも…期待はApple Intelligenceの利用
家族間の情報共有、気づけば「言った」「言わない」のバトルへ
家族6人で情報共有するとなると、よく起こるのが「言った」「言ってない」の問題。最終的に言い争いに発展することもしばしばです。
例えば、こんな感じ。
二男: これから遊びに行くね!
夫: えっ! 理髪店の予約入れてあったでしょ!?
二男: そんな予定言った?
夫: 伝えた!
そして、家庭内紛争の火種ともなりかねないのが学校からの大量のプリント類。当初は、定番といわれるホワイトボードや冷蔵庫に貼り付けていましたが、なぜか紛失してしまうことがあり、その度に怒号が飛び交う始末。
特に反抗期に差しかかった二男とのやりとりは、状況が悪くなりがちです。本人は「プリントはホワイトボードの大きなクリップに挟んだ」と主張しますが、プリントの束を見返しても、授業参観のプリントは出てきません。最終的に、「わからないものはわからない」という不機嫌な二男と、予定を立てたいのに立てられない母のイライラがぶつかり、大きな声が家じゅう響き渡ります。
紛失なのか、提出忘れなのか、真実はともかくとして、提出が必要なプリントだったりすると、ひたすら捜索に時間を費やしていました。
【解決策①】プリントのデータ化、紛失しても印刷して提出できる
こんな事態を何とか改善したい! と着手したのが プリントのデータ化 です。そもそもデータ化を思い付いたのは、在宅勤務になった夫。ファイル名に日付を入れると、いつどんな内容のプリントが配布されたのか管理しやすくなると考えたようです。データ化をしておけば、必要なときにいつでも見返せるほか、プリントを紛失してしまっても、プリントアウトし直して提出ができます。
まず、第1のアクションは、子供たちが持ち帰ったプリントをその日のうちにスキャナーでデータ化すること。二女はこちらから言わずとも、リビングテーブルにプリントを置いていてくれるのですが、二男からは「後で出す」の返事でかわされることが多いため、「言われたときに出す!」ことをルールに。根気強く声かけをし続け、データ化しています。
我が家では、 データ化したプリントをクラウド上に保存 しています。パソコンからはもちろん、通勤時間などの隙間時間を使って、手元にあるiPadやiPhoneで、どこからでも確認することが可能に。事前にプリント内容を把握することで、帰宅後にすぐ処理して子供に持たせることができるようになりました。
【解決策②】iPhoneでデータ化を簡単に、ファミリー共有をフル活用!
スキャナーを使うのが面倒なときは、iPhoneのメモ機能を使ってデータを共有しています。きっかけは、家族全員がiPhoneユーザーだったこと。iPhoneには 「ファミリー共有」という便利な機能があり、使わない手はない と思ったのです。手軽に取り込めて、すぐにデータを共有できるのがおすすめです。
手順も簡単。まずは、iPhoneの[メモ]アプリを開き、[新規作成]-[書類をスキャン]をタップ。カメラをプリントにかざすだけで撮影できます。画像化されたプリントデータは、メモ内に「学校関連」のフォルダをつくって管理し、大学生の息子を除いた5人で共有しています。特に便利なのは、 プリントのタイトルが自動でファイル名になること! 楽に整理もできて、子供たち自身も必要に応じていつでもプリントを確認できるようになりました。
なお、注意点は、子供がプリントを学校に忘れて来たときや紛失したときの対応です。残念ながら、この部分はITを使った仕組みをいくら取り入れても、本人との対話をすることでしか解決できません。
我が家では、「プリントを忘れない・失くさないための仕組みづくりが必要」と繰り返し伝えて、子供自身がメモを記録することを勧めています。ですが、なかなか行動には結びつかないのが悩みです。
そもそも、長男や長女を見ていると、メモを取るという習慣がないように見受けられます。二男も、小学校の高学年からiPhoneやパソコンを使っているので、紙にアウトプットする習慣がないのかもしれません。とはいえ、忘れない仕組みづくりの方法の1つとして、メモを取ることを覚えていて損はないはずです。
【解決策③】カレンダーアプリで家族の予定管理、カオスな状態を回避!
そして、データ化の次に必要だと思ったのが、 スケジュールの管理 です。これまでは、学校や家族の予定を壁掛けカレンダーに記入し、イレギュラーな通学・帰宅時間や、お弁当の有無などを書き込んでいました。4人分の予定が重なると、次の日の枠までなだれ込んでしまう日もあります。
何とかしたいと思って、iPhoneの活用方法を調べると、カレンダー機能がヒット。 プリントのデータ化を済ませた流れで、その予定をカレンダーにも登録、 反映させることにしました。
[カレンダー]アプリで家族カレンダーを追加し、家族6人と共有。学校行事はもちろん、プライベートな予定も6人分にそれぞれ色を振り分けて登録します。「予定が入ったら、まずカレンダーに登録」を家族のルールとしたことで、部活や塾、バイトなど、活動時間がバラバラで家を出たり入ったりの日々でも、予定を把握できるようになりました。
急な時間変更やお知らせがあるときは、グループLINEが便利です。今のところLINEだと子供たちの反応が早く、「帰りが遅くなったので、お風呂掃除当番を代わって」「手が空いている人、ごはんを3合炊いて」など、突発的なメッセージが飛び交うことも。
プリントの管理や予定の管理など、ツールを使うために家庭内でルール化するのは、子供たちにとっては窮屈で嫌なことかもしれません。しかし、案外ルール通りに進めている場面を見ると、子供自身もツールを使うことで便利さを感じている様子。 やみくもにルールをつくるのではなく、ルール化した後でどんな恩恵があるのを伝えて納得してもらうことが大事だと感じます。
【発展編】スマートスピーカーで予定管理、話しかけて予定を登録
最近わずらわしいと感じていたのが、毎朝の子供たちからの質問攻めです。出勤・通学前の忙しい時間帯に、天気や塾の予定などを矢継ぎ早に聞かれて少々パニックに……。自分で完結できることは、自分で済ませてほしいと思い、 スマートスピーカーを利用して、子供たちの質問に対応できるようにしました。
きっかけは、「へい、Siri、(出張先)の今日の最高気温は?」と夫がスマートスピーカーに話しかけているのを見かけたこと。「これなら子供たちにもできるかも!」とひらめき、“チャットボット”風に、家族で共有できるツールとして使ってみることにしたのです。
「 HOMEPod mini 」をリビングテーブルに置いたところ、「○○市は、今日は傘が必要?」と聞くことが日課となり、「ねぇ、Siri、〇月〇日に美容室の予定を入れて!」と予定の登録にも利用。HOMEPod miniは、iPhoneのカレンダーと連動しているので、面倒くさがりの子供たちは、 HOMEPod miniに話しかけて予定を登録する 方が気楽な様子です。
先日、テスト期間で帰宅が早まる二男は、「ねぇ、Siri、○日と○日は弁当なし、と予定を入れて!」とHOMEPod miniと会話(この情報、お弁当をつくる筆者としてはとても重要)。傍らでうなずく筆者を横目に、「ねぇ、Siri、弁当じゃないならオムライスが食べたいなぁ」と二男。対するSiriの答えは「オムライスいいですね」と二男を後押し。翌日の晩ごはんの食卓には、オムライスに似た「オムそば」が並ぶことになりました。
【課題と期待】スマートだけど抜けてるところも…期待はApple Intelligenceの利用
HOMEPod miniを子供の話し相手にした我が家ですが、コンシェルジュのような「チャットボット」として使用することは、まだ少し先になりそうです。というのも、3件予定がある日に「今日のスケジュールを読み上げて!」とリクエストしても、1件の予定しか読み上げてくれず、もう少し研究が必要かも……。
筆者が期待しているのは、2025年4月に日本語対応を開始したAppleのAIプラットフォーム「Apple Intelligence」です。生成AIの技術がiPhoneやiPad、Macに搭載され、Siriの機能も強化されます。対応デバイスの確認とOSアップデート、初期設定が必要ですが、例えば、「ねぇ、Siri、今日の予定と天気をそれぞれ教えて!」といった少し複雑なリクエストにも対応できるようです。
我が家のApple製品は、Apple Intelligenceに非対応のため、しばらく情報共有はこのまま。興味がある方は、ぜひ取り入れてみてもいいかもしれませんね。
我が家では、本稿で取り上げたデバイスやアプリで6人分の予定をスムーズに共有できるようになりました。家庭内のIT化を進めることが、大家族ならではの家庭円満のポイントと捉え、これからも便利なツールや仕組みを積極的に取り入れたいと考える次第です。そして、それぞれが「予定や情報を家庭まで持ち帰ることが何より大事」ということもあらためて実感しています。
















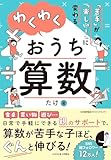

















![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)