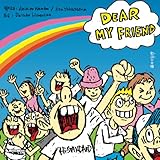レポート
教育情報・データ
全国初、大分県に「遠隔教育配信センター」開所 Zoom Roomsで難関大合格と生徒減対策を支援
2025年5月14日 06:30

大分県教育庁は4月14日、複数の学校へ同時双方向型授業を行える「遠隔教育配信センター」(通称:OitaTEC:オオイタテック)を開所し、記念式典を開催した。同センターは、難関大学等を志望する理系選択者を対象とし、多様で質の高い高等教育を提供を目指す。遠隔による学習支援(SOP:生徒進学支援オプション)も合わせて提供する「大分モデル」の確立を進める。
県立高校で双方向の遠隔授業を行う「遠隔教育配信センター」が開所
大分県教育庁では、令和6年3月に「大分県立高等学校未来創生ビジョン」を策定。魅力ある学校の実現に向けた教育基盤の整備を目的に、遠隔配信を活用した次世代型の教育システムの構築を開始した。今回の「遠隔教育配信センター」(通称:OitaTEC:オオイタテック)は、これが実現化されたもので、教育委員会の単独組織としての設置は全国初となる。
この遠隔教育配信センターは、大分市に位置する大分上野丘高等学校の特別教室棟1階部分に設置され、延床面積は319.5㎡。防音・吸音のスタジオである専用配信室を8室設置。配信システムにはZoom Roomsを採用し、スタジオ内には大型ディスプレイとNeatのバータイプのデバイスを設置している。
ミーティングスペースのほか、教員用の執務室もあり、席はコワーキングスペースのようなデザインのフリーアドレス。執務室に固定電話はなく、各教員はZoom Phoneを利用することで場所に縛られず、働き方改革にも寄与する。
現在、公立高校に向けた遠隔授業は、大分県以外にも北海道、鹿児島県、長野県、静岡県など複数の県で開始されているが、大分県の遠隔教育配信センターの設備は特に充実しており、教員も生徒も違和感なく授業が行える。配信を行う教員は、受信校に兼務発令された専任教員。令和7年度より週12時間の配信授業から開始し、令和10年度には週176時間の配信を予定している。
遠隔授業は同時双方向授業で行われ、2校が合同で実施。令和7年4月当初は県立高校4校で先行導入し、臼杵高校と宇佐高校、佐伯鶴城高校と日田高校の生徒が合同で授業を受ける。さらに、長期休業中には大分県内の28の普通科等設置校の生徒を対象に特別授業も行われ、遠隔授業と合わせた「大分モデル」の確立を目指す。
4月14日に行われた遠隔教育配信センターの開所式では、大分県知事の佐藤樹一郎氏があいさつし、大分県で以前から遠隔教育に力を入れ、スタンフォード大学の遠隔講座や、県内の大学と連携した取り組みなどにも言及。「今回の遠隔教育配信センターの設立で、より包括的に遠隔教育が前進し、地域の活性化につながることを期待する」と述べた。
大分県教育庁 教育長の山田雅文氏も遠隔教育配信センターの配信高校を順次拡大していくと説明。大分モデルの特長を、2校合同で遠隔授業を行うことで切磋琢磨できること、遠隔技術を活用した学習支援であることを説明し、「大分県が全国に誇れる先進モデルとなり、大分県の生徒たちが遠隔教育で可能性を最大限生かせるよう期待する」と語った。
大型ディスプレイに教員が“ほぼ等身大”で表示される遠隔授業
開所式では、大分県教育庁 遠隔教育配信センター所長佐藤哲也氏が遠隔教育配信センターによる遠隔授業の詳細を紹介。同時双方向授業の遠隔授業は、令和7年4月から県内の4校で先行導入し、令和8年4月からはさらに8校、令和9年4月に5校が追加され、令和9年までに17校が受信校となる。
遠隔授業は遠隔教育配信センターは令和7年度は専任の教員9名とスタッフ3名で運営。2校同時に配信し、臼杵高校と宇佐高校、佐伯鶴城高校と日田高校の生徒が合同で授業を受ける。
開始当初は、2年生の理系選択者のうち難関大学を志望する生徒が対象で、各校から10名程度が参加し、今年度は合計42名が登録している。今年度の配信教科は数学と英語で、その生徒たちが翌年度、3年生になるタイミングで持ち上がり、3年生でも継続実施。理科の物理と化学も配信教科として追加される。この物理や化学の教員はすでに遠隔教育配信センターで来年度の準備を開始している。
参加する生徒たちの教室と、配信する教員のスタジオの両方には、マイクやカメラが一体になった「Neat Bar Pro」が設置された複数の大型ディスプレイが整備され、配信システムにはZVC JAPANの「Zoom Rooms」が使用される。
生徒たちはこの教室前面の大型ディスプレイに加えて、1人1台端末も利用。ディスプレイに表示される教員はほぼ等身大で、参加する生徒たちからは「普段の授業と変わらず、違和感はない」という感想が多いという。配信側のスタジオでも受信側の教室でも、ボタン1つでつながるために特別なマニュアルも用意されていないという。
生徒減による将来的な課題に「大分モデル」で対応
大分県教育庁 遠隔教育配信センター 次長 釘宮隆之氏は、今回の取り組みの根本には、同県の課題として出生者数の減少とそれによる人口減があると説明している。中学校卒業者の比較では、平成22年3月卒業の11,891人に対して、令和7年3月卒業は9,740人と、15年間での減少率が約18%に上る。予測ではさらに今後15年間で1/3以上減少し、令和21年3月の予測では6,235人と減少率が36%にまでなる。
大分県では前述の通り、令和6年3月に「大分県立高等学校未来創生ビジョン」を策定後、大分県の長期計画にも遠隔教育システムの活用が明記され、1年間の準備期間を経て遠隔教育配信センターを開設した。
生徒数の急減により、すでに県内の高校では同一クラス内に様々な学力層の生徒が在籍するようになっている。遠隔教育システムの環境整備は人口減少によるこうしたさまざまな課題に対応する。
また、大分県で行われている遠隔教育には、今回の配信センター方式による双方向型遠隔授業のほかに、令和3年から実施している「学校間連携方式」もある。これは商業や福祉などの、専門科目を実施する高校からほかの高校へ遠隔授業を行うもので、令和6年以降も継続される。
遠隔教育配信センターが中心となる「大分モデル」の特長は、遠隔による学習支援(SOP:生徒進学支援オプション)にもあり、長期休業中に大分県内の28の普通科等設置校の生徒を対象に難関大学志望者向けの特別授業をリアルタイム配信したり、動画教材のオンデマンド配信も実施。遠隔授業を受ける生徒へは、毎日16時30分~18時15分の間「放課後オンライン質問室」を開設し、Zoomで先生と1対1の個別指導なども実施する。
Zoom RoomsとNeat Bar Proで授業動画をテキスト化し、倍速で復習も
今回の遠隔教育配信センターの配信に「Zoom Rooms」が採用されていることについて、ZVC JAPAN 株式会社 執行役員 公共・文教営業本部 営業本部長の野澤さゆり氏は、「今まで対面だけだった授業をデジタルにすることで、そのデータによる活用は無限に広がっていく」と語った。
生徒たちはスマートレコーディングを使って見直したい部分を章立てから見つけ、その部分だけを見返して復習したり、倍速で見ることもできる。実際に、遠隔教育配信センターで配信された授業はすべて録画されており、復習用として、生徒たちへ授業日の夕方にはAIが自動で文字起こしした録画データを公開している。
教員側も生徒との定期的な面談内容をzoomで録画しておくことで、生徒や保護者に提供したり、翌年の担当教員に引き継く際に役立てることが可能に。フリーアドレスの執務室ではZoom Phoneが採用されており、教職員がどこにいても学校にかかってくる電話に出られるしくみになっている。また、その会話の内容を録音することで文字起こしが可能になり、会話中にメモを取る必要もなく、要約やタスク化もできる。
また、ディスプレイ上部に設置されている一体型デバイス「Neat Bar Pro」について、Neatframe株式会社 代表取締役 柳澤久永氏が説明。Neat Bar Proはzoomのアプリケーションと一体型で使うバータイプのビデオデバイスで、マイク、カメラ、スピーカーのほか各種センサーが搭載されている。同社の製品は会議室はもちろんオープンな場所でも使えるよう意識されて設計されている。一定の範囲内に音が届き、参加者の表情まで相手に届くような、臨場感のあるコミュニケーションを支援する。
特にマイクの集音性能の良さを誇り、ノイズは除去して文字起こしを効率化。AIにより複数人の顔を判別して表情をアップで表示し、表情がより伝わることで感情や思いを共有できる。柳澤氏は、「双方向型の授業や、生徒同士のやりとりに、この機能がより活用されるのではないか」と期待を込めた。実際に生徒たちの反応も非常に良く、「イヤホンで聞くよりも音が良い」という感想もあるという。
遠隔教育配信センターの釘宮氏は、他県の配信センター方式の取り組みと大分県の施策との違いを、「今足りていない場所を支援する取り組みではなく、将来的な生徒数減に今から備えるためのもの」と説明。数年前から実施されている北海道の遠隔授業配信センターの事例などからも学びながら、学習支援もパッケージになっていることが特長だと紹介した。
今後の展開について釘宮氏は、「国語など、ほかの教科も配信してほしいという希望も上がっているが、まずは3年間で17校に展開することを目標にしていきたい」と語った。また、遠隔授業の最大の課題が机間指導ができないことだと話し、教室の中で生徒たちの近くでアドバイスをしたり、生徒たちから質問ができるような感覚をアバターで実現する「机間指導用ロボティクス」の実験も進めていると説明。全国に先駆け、いち早く実現したいと語った。





















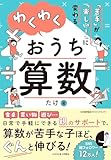













![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)