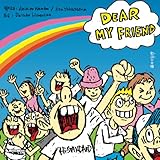トピック
生成AIからのヒントに子供たちはどう反応する?~図画工作のアイデア出しと振り返りサポート
- 提供:
- コニカミノルタジャパン株式会社
2025年4月15日 06:30

小学校での生成AI活用の試行が進む中、群馬県教育委員会は美術と図画工作で生成AIを効果的に活用する実証授業を2025年1月に行った。使用したのは、コニカミノルタの学習支援サービス「tomoLinks」に組み込まれている、年齢制限なく利用できる生成AI学習支援機能「チャッともシンク」。生成AIの活用目的に合わせて丁寧に最適化してのぞんだ授業の様子と、関係者の思いを紹介する。
好きなものを詰め込んだ缶バッジをデザイン!

この日の6年生の図工の時間は、自分の好きなものをデザインして自分を表現する缶バッジを作るのがテーマ。授業を担当した同校の富山亜紀穂教諭は、見本として好きなものの絵がたくさん散りばめられた缶バッジのデザインを見せて、色、形などのバランスを意識していろいろなアイデアを出し、スケッチするように呼びかけた。
そして「今日はアドバイザーが追加されています」と富山教諭が紹介したのが生成AI。普段の図画工作の時間と違って各グループに1台ずつタブレット端末が置かれ、生成AI学習支援機能「チャッともシンク」が使えるようになっていた。この生成AIはあらかじめ授業目的にあわせて最適化されていて、「好きなもの好きなところさがし」、「スケッチお助けロボ」、「振り返りお助けロボ」の3つのモードを切り替えられるようになっている。
言葉を交わしたり生成AIに聞いたり
作業時間に入ると、近くの児童同士で会話をしながらまず自分の好きなものを文字で書き出していった。食べ物や動物、スポーツ、習いごとや趣味に関わるものなどが多いようだ。ある程度書き出したところですぐにデザインにとりかかる児童もいるが、そこでいったん手が止まっている児童が多い。「好きだけど絵にする技術がないっ!」という声も聞こえてくる。
このあたりから生成AIに手を伸ばす児童が増えてきた。初めは「○○の画像を出して」とウェブ検索の感覚で見本になる写真や絵を見ようとしている様子が多かったが、使用した生成AIはもともと画像を出力しない仕様で、会話の方向性は児童の発想を手助けするように最適化されている。
例えば「スケッチお助けロボ」モードの場合、児童が自分の好きなものを羅列して「これをもとにして6個ぐらい絵を描いて」とAIに作業させようとすると、AIは具体的な描き方を示す代わりに、創造的な視点を与えるヒントを提示しつつ、「まずはスケッチを始めてみましょう」と促す。このヒントは、意図的に具体的なHow Toを避け、児童が自分自身で「表し方を考えたり材料や用具を工夫したりしながら作品を作り上げる」という創造的な学びの機会を奪わないように工夫されている。そんな挙動に児童もすぐに気付いて、AIのヒントを参考にして絵を描こうとしていた。
児童が授業で生成AIに初めて触ったのはこの授業の前日。安全に動作することを検証した「おしゃべり」モードで自由な会話を体験し、授業前の休み時間も興味深そうに触っている姿があった。まだものめずらしい存在なはずだが、授業中に取り合いになったり生成AIに夢中になって課題の手が止まったりするということはない。お互いに喋ったり声をかけあったりする中に、グループの一員として生成AIも1台あるという雰囲気だ。
授業の半ばくらいで先生が声をかけ、全員席を立ってお互いのデザインを見てまわった。デザインのアイデアを膨らませていくつもデザイン案を描いている児童は一部で、まだひとつ目のデザインに取りかかっている児童が多い。富山教諭が、児童の作品の工夫を紹介して、再び制作に戻った。
生成AIからのヒントで一歩目が踏み出せる
生成AIが効果を発揮していた場面のひとつが、絵にしたい好きなものは見つけられていても、どうやってその絵を描いたら良いかわからないときだ。「レッサーパンダってどんな形?」、「ドラゴンの特徴は?」、「本をどう描けばいいかわからないけどどうしたらいい?」、「ナスの描き方」……などと具体的に聞いている児童が多く見られた。
生成AIは文章でヒントを示すだけだが、それを手がかりにとりあえず手を動かし始めることができる。そうしているうちに誰かと話して意見を求めたり、また生成AIに追加質問をしたりして、だんだん形にしていくことができている様子だった。
本が好きで本の描き方を生成AIにたずねていた児童は、振り返りの際に「今まで本を描くことが難しかったけど、本を少しだけ描けるようになった」と書いていた。生成AIが良いサポートになったことがわかる。他にも「わからないことを生成AIに聞くとすぐに答えてくれたし、わかりやすかった」、「AIの力を借りて描きたいものの描き方や着色の仕方なども詳しく教えてもらって絵を描くのが簡単になりました」など、AIからのヒントをプラスに捉える振り返りの声が複数見られた。
人同士のサポートは大きな力になる
一方で生成AIだけではなく、人の力を感じるシーンもあった。生成AIが具体的なヒントを文章で提示しても、そこから簡単に絵を描ける児童ばかりではない。富山教諭は児童の様子を見て適宜声をかけ、必要に応じて対話をしたり図示したりしてサポートしていた。教諭との会話で描くきっかけを得られ手が動き始めていたのが印象的だ。
また、児童同士で、「これどうかな?」「色つければわかりそう」とか、「ここの色、黒がいいかな……」「え?青じゃない?」などと気軽に言葉を交わしながら作業を進めていて、作品を客観視することに役立っている様子だった。このように絵を見せ合って人の感覚で意見を言うというのは生成AIにはできないことだ。
一方で生成AIは、アイデアの最初のきっかけを提示したり、バリエーションを増やしたりすることはとても得意なので、グループに得意分野の違う相談相手がひとつ増えたような状態だ。描き方をたずねるだけでなく、中には「面白い絵を教えて」と問いかけている児童もいた。何か面白くできないかと、友人に相談するのに近い感覚だろう。生成AIからの提案を参考に、描いていた絵のひとつをキャラクター化しようとしている様子だった。
なお、絵が好きだったり得意だったりする様子の児童ほど生成AIを使う気持ちはない様子で、全く触れずに描き進めていたのが象徴的だった。
生成AIのアシストは児童自身の発想の余白がある
今回使用した生成AIは絵を描く手がかりになるとはいえ、正解らしき画像を出すわけではないので、児童は文章で得たヒントをもとに自分で考えるしかない。富山教諭は今回の生成AIの役割について次のように振り返った。
「画像を見ると『この通りに描きたい』という気持ちが強くなってしまって、その通りでないと失敗だと捉えてしまう子もいますが、文字で読むと、その子自身の解釈が入る余白があると思うんですよね。例えば生成AIが『細長い三角』と説明したとしても、どのくらいどのように細長くするのかということは人の感覚によって大きく違います。正解は出てこないので、自分なりに納得できればそれがその子なりの表現になってくるのだと思います」。
普段はウェブの画像検索で写真などをすぐに参照できる世代だけに、今回の生成AIが検索感覚で画像が出てこないことや、ヒントは提示してもこれが正解と思わせるような回答をしないことなどが、児童が自分で考えるきっかけになっていたようだ。
一方で、「子供の発想、構想やつまずきを拾って道に乗せるのは私たち教員の役目だと思っていたので、今日はその部分に生成AIがどれだけ入りこんでくるのかが未知数でした。子供がどちらを頼るのか勝負しよう、というような気持ちもありました」と富山教諭は話す。
実際に富山教諭が関わったからこそ動けた児童もいれば、生成AIから小さなサポートを受けていた児童たちもいた。サポートといっても人ができることと生成AIができることは違うので、それぞれの良さを生かしたサポーターとして共存できるものなのではないかという印象を受けた。
苦手な振り返りが書きやすくなった!
もうひとつ、生成AIが活躍したシーンが振り返りの時間だ。「振り返りお助けロボ」モードの生成AIに、児童が「がんばったところを振り返って」と問いかけると、「この缶バッジのデザイン、どんなところにこだわったのかな?」などと小さな質問を投げかけて児童の感想を引き出していった。使用した児童は、「振り返りが苦手なんですけど、いつもよりはやく書けました。これからも使ってみたいです」とうれしそうに話した。
振り返りで利用したのは少数の児童だったが、特に自分の考えを整理することに苦手感を持つ児童にとっては、プラスのサポートになる可能性が見えた。
目的に応じた丁寧な最適化が必須
今回の授業に向けては、群馬県教育委員会事務局 総合教育センター 義務教育研究係 指導主事の豊岡大画氏を中心に、事前に入念な検討と準備が行われていた。生成AIの利用価値を検証するために注目したのが、児童の気づきを「深掘り」する役割と、実際に動いてやってみる「身体性」を促す役割だ。そこで、図画工作の自分の好きなものごとを見つけたり活動を振り返ったりする深掘りの過程と、好きなものを絵にする身体性を伴う作業の場面で、生成AIがどのように寄与するかを確かめたのだ。
これらの目的別に生成AIを最適化する必要があったため、「チャッともシンク」の開発スタッフが設定のため伴走した。「チャッともシンク」には、管理者機能で生成AIのふるまいを決めるシステムメッセージを設定できる。どのような反応をどのような口調でするのかなど、期待する役割像をあらかじめ指定できるのだ。今回は検証のために豊岡氏の要望を元に開発スタッフが何通りものシステムメッセージを書いて調整を繰り返したが、日常の運用では、教員が自分でシステムメッセージを設定して授業の目的に最適化して児童に利用させることができるようになっている。
なお、豊岡氏らは、端末利用時に個人の世界に閉じてしまうことを避けたいと考え、端末をグループに1台置き、複数の児童が一緒に画面をのぞきこんだり交代で使ったりすることを促した。児童の協働や創造性を生成AIが阻害しないように慎重に検討を重ねて授業を迎えたことがわかる。
この日の授業で生成AIを活用した子供たちには、細やかな変化やプラスの影響が見られたものの、美術や図画工作のあらゆる場面において思考を促すために生成AIが有効かという点については、豊岡氏は現時点での評価に慎重だ。しかし、本授業を含む実証全体を通して、「鑑賞」の場面や「振り返り」のプロセスにおいて、一定の効果があると見ている。
また、本実証に関わった教育委員会関係者からは、「生成AIを活用した授業について、学びの一連のパッケージの中に適切に組み込まれることで初めて意味を持つ」、「教師の意図が明確に反映されていないと十分な効果が得られず、授業構想がしっかりしていることが重要」という指摘があった。
これらをふまえ豊岡氏は、生成AIは単独で効果を発揮するものではなく、教員の経験や専門性と組み合わせることで、より価値のある学びを生み出せることが明らかになったと分析、「生成AIはこれから教育でも避けて通れないのでできちんと向き合う必要があると思っています。その際に、子供たちに対するリスクに線を引いて、安心安全で教育に資する使い方でなければいけないので、教育現場から、より良く使う道を提案したいと考えています」と語った。
テクノロジーが発展するスピードにただ流されるのではなく、こうして子供たちの学びを豊かにするテクノロジーの使い方を検証する試行錯誤が各所で行われている。簡単に答えの出ることではないが、教育関係者の検証の努力が新たな学びの可能性に生かされることを期待したい。











































![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)