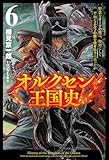レポート
教育実践・事例
堅苦しさナシ!子供たちの学びと成長を地域で共有、大阪府枚方市が「GIGAフェス」開催!
2025年2月10日 06:30
1人1台タブレット端末の活用が進み、学びの形が変わる中、家庭や地域との連携がより重要になっている。こうした変化を保護者に理解してもらうには、学校だけでなく教育委員会が保護者や地域に働きかけることも重要だ。
そうした中、大阪府枚方市は2024年12月25日に保護者も参加できる「枚方市教育の祭典 GIGAフェス2024」を開催した。教育委員会主催のイベントとしては珍しい工夫が各所にあり、楽しい雰囲気にあふれる教育フェスとなった。各校の探究学習の発表を核とした当日の様子をレポートする。
お笑い芸人がステージ進行も!市長がHADOに挑戦
GIGAフェス当日はちょうどクリスマス。会場の枚方市立総合文化芸術センターには、前日に終業式を終えた子供たちが保護者と共に続々と集まってきた。会場内には、AR(拡張現実)や生成AI、VRなどのデジタル技術やマインクラフトの教育コンテンツを体験できるコーナーがあり、子供たちが気軽に立ち寄って楽しんでいて、正に「フェスティバル」という雰囲気だ。
この日メインとなる探究学習の発表会は小ホールのステージで開催され、オープニングは枚方市立さだ小学校のピルナール合唱団のクリスマスソングが飾った。子供たちのまっすぐな歌声に会場があたたかい雰囲気になったところで、進行を担うゲストのお笑いコンビの祇園、ラニーノーズが登場。どちらのメンバーも枚方市にゆかりがあり、子供たちのPBLの成果発表を来場者と共に見守った。
枚方市の小中学校では2024年度より、身近な問いや地域の課題解決をテーマにしたPBL(Project Based Learning:課題解決型学習)に取り組んでいる。枚方版PBLは、地域の宝である子供たちの未来への可能性を伸ばすためのものであるということから、「ヒラカタノタカラプロジェクト」と呼ばれている。この日は1年目から取り組んでいるモデル校がその成果を発表する場となった。
枚方市長の伏見隆氏は挨拶に立ち来場者にメッセージを伝えたあと、そのままステージ上で子供たちと共に「HADO」を体験した。HADOはVRゴーグルと腕に取り付けたセンサーで楽しむゲームアクティビティで、手のさまざまな動きで攻撃や防御をして競い合う。市長とラニーノーズによる大人チームは、派手なアクションで子供チームからの攻撃をよけたり技を繰り出したりして見せ、会場は大いに盛り上がった。教育イベント的な堅さがなく、すっかり楽しい雰囲気になったところで子供たちの発表が始まった。
小学生は興味と発想を大切に提案!
枚方版PBLの発表は小学校2校と中学校3校が行った。枚方市立東香里小学校の4年生は「いのち輝く未来大阪のデザイン 未来大阪プロジェクト」と題してチームごとにテーマを立てて探究学習に取り組んできた。例えば地域を観光で盛り上げるためにお好み焼きをモチーフにしたパンケーキを試作したり、犯罪を減らすために自転車のサドルの盗難防止グッズを考案したりと、さまざまなアイデアが詰まったプロジェクトの様子を次々と元気に発表した。
枚方市立氷室小学校は、4年生が地域を盛り上げるお祭りの企画をしたこと、5年生は地域の魅力を伝えるパンフレット制作をしたこと、6年生は地域の課題解決に取り組んだことをそれぞれ発表した。6年生は、例えば空き家問題や少子高齢化などをテーマにしていて、関連するデータや地域の状況を調べた上で解決策を考えられていた。
中学生は現状を丁寧に把握して根拠のある提案
中学生になると、プロジェクトの実行力も上がる。枚方市立枚方中学校からは「能登半島被災者支援プロジェクト のとプロ」のメンバーが、能登半島沖地震の支援のために募金を行ったことなどを発表した。枚方市に招かれた能登の子供たちとの交流会にも参加し、避難所生活の大変さや実態について直接体験を聞いて、災害を伝え支援を継続することの重要性を改めて感じたという。今後も活動を継続するということだ。
また、枚方市立第二中学校、枚方市立楠葉西中学校からは、防災や多文化共生、ルールメイキングなど複数のプロジェクトの発表があった。中学生になると、現状を把握するために、資料を調べたり他の地域の事例を調べたり、インタビューを行うなど、ていねいな調査ができている。そして調査でわかったことを材料や根拠にして解決策を考えるというステップを踏んでいて、小学校段階と比べて探究の質が中学生らしく深められていた。
発表全体を通じて、小学生ならではの良さもあれば、中学生らしいアプローチもあり、それぞれの良さと特徴が見えた。学年による違いが、成長の過程とも言えるのだろう。ステージ上で発表する子供たちはとても一生懸命で時にほほ笑ましく、見ていて応援したい気持ちになる。保護者にとっては、日常では気付かない子供たちの成長を実感するまたとない機会になっただろう。
ARや生成AI、人気のマインクラフトを使った体験授業も!
会場内の体験コーナーでは、来場者がデジタル技術を使った学びや制作を楽しんだ。AR技術を体験できるコーナーを運営していたのは大阪府立牧野高等学校の美術部の生徒。参加者はReality Composerというアプリで3Dオブジェクトを作り実際の風景と合成するARを体験し、その写真を使ってクリスマスカードに仕上げた。高校生のサポートを受けながらiPadを使って直感的な操作で作成できるので、子供も大人も楽しんでいた。
また、生成AI体験のコーナーは関西外国語大学の学生が運営した。Canvaの生成AI機能でオリジナルのクリスマスツリーを作るというコンセプトで、発想豊かなクリスマスツリーが並んだ。牧野高等学校も関西外国語大学も枚方市内にあり、地域のつながりが感じられ、高校生や大学生が小中学生と直接関わる貴重な機会になっていた。
さらに、マインクラフトのコーナーでは、立命館小学校の正頭英和教諭が特別授業を実施。参加した子供たちは、金融リテラシーを育むために開発された教材「クエスト オブ ファイナンス」を体験した。子供たちのミッションは大魔王から村を守ること。そのためには制限時間内に100コイン集める必要がある。参加者にはコインを集めるための情報が掲載された「勇者新聞」が配布され、その情報を読み解きながらマインクラフト上でコインを集めるさまざまなクエストをこなしていった。
この教材はSMBCコンシューマーファイナンスが正頭教諭らの監修で開発したもので、Minecraft Educationがあれば無料で利用できる。冒頭で紹介したHADOも体験を受け付けていて、これら民間からの出展も加わって体験コーナーがにぎわった。保護者としても、子供を連れて参加するイベントにこのような体験コーナーがあると、子供のモチベーションを維持できてとてもありがたいのではないだろうか。
楽しいフェスで枚方市の教育と子供たちの姿を伝える
枚方市教育委員会 学校教育部教育研修課ICT推進グループの浦谷亮佑氏は、今回のGIGAフェスのねらいをこう話す。「GIGA端末が学校に入り枚方の子供たちがどのような学びをして成長しているのかということを、市民や保護者の皆さんに知ってもらい理解を広げたいと考えて企画しました。教育のイベントというと堅くなりやすいので、楽しい『GIGAフェスティバル』として、多くの皆さんに集まってもらえるようにしています」。
同課主幹の大潮一夫氏も、「体験と発表の両方を打ち出したイベントで、広く枚方市内のとり組みと、子供たちが未来に向かって学ぶ姿を発信できたのではないかと思います」と振り返る。GIGAフェスティバル自体は4年目の開催で、PBLの発表は前年度はオンライン開催で今回は初めてのリアル開催となる。今年度は枚方版PBLが始まった1年目で、子供が主体になって取り組んできた普段の姿をフェスティバルの場で発表することができた。同課課長の永山宜佑氏は、「子供たちは堂々と発表していて、大きなホールのステージに立った経験は、今後の自信になっていくのではないかと思います」と語った。
ステージに上がる子供たちの手にはGIGA端末のiPadがあり、体験コーナーでもiPadが活躍していた。子供たちのPBLの内容やプレゼンテーションのスライドからはiPadが日々の学習活動に馴染んでいることが伝わってきて、枚方市のICTの普段使いの延長線上にある、非常に明るい教育フェスティバルだった。子供たちや教育の姿を地域に広げていくためには工夫も必要で、そのひとつの姿として他の自治体でも参考にできることがあるのではないだろうか。











































![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)