トピック
落下に強くて滑りにくい、約590gの軽量タブレットにもなる2in1 PC「dynabook K70」
GIGAスクール第2期のWindows PC選び③
- 提供:
- Dynabook 株式会社
2024年6月4日 06:30
GIGAスクール第2期の児童生徒用Windows PCとして、Dynabook 株式会社が提供しているのは「dynabook K70」。本体からキーボードを取り外してタブレットとして使えるデタッチャブルタイプで、重さ約1,097g、タブレットのみの場合は約590gと非常に軽い。教室ではノートPCとして利用し、校外学習や持ち帰りのときはキーボードを外して軽量なタブレットとして利用できる。
同社 国内PC事業本部 公共・文教営業本部 主査 西村聖二郎氏はdynabook K70について、徹底的に「子ども目線」にこだわって開発したと語る。
「GIGA第1期のときは約100万台ほどご採用いただき、先生方からはバッテリーの持ちが良いと評価をいただきました。一方で想定外の扱い方をされるケースも現場からフィードバックをいただいており、GIGA第2期ではさらに改良を重ねました。子ども目線に寄り添って、様々なアクシデントからデバイスを守る堅牢性を備えています」(西村氏)。
バッテリー駆動時間約16.8時間、落下によるアクシデントを強化
dynabook K70は、10.1型の2in1 デタッチャブルノートPCで、CPUはインテル Pentium Silver N6000 プロセッサーかインテル Celeron N4500 プロセッサーを選択できる。メモリーも4GBと8GB、ストレージは64GBと128GBから選択可能で、LTE対応モデルなど希望のスペックを組み合わせることができる。
最大の特長は、バッテリー駆動時間で約16.8時間を実現。GIGA第1期のときも児童生徒用PCは約16時間の駆動時間を備えていたが、そこからさらに改善された。西村氏は「実際にGIGA第1期モデルが3~4年使われましたが、dynabookのバッテリーは劣化が少ないと現場から評価をいただきました。今回はさらに改良して同仕様の端末の中でも最長の駆動時間を実現しています」と語る。
また堅牢性も強化しており、学校現場でよくある落下によるアクシデントに強い構造を採用。dynabook K70の本体外周をゴムのような弾力性と硬質プラスチックの強さを併せ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)で覆うことで、落下による衝撃を守る。
特にコーナー部分には大きな角度の丸みを持たせて内部をリブ構造にし、落下による力を分散させることで本体内部への影響を緩和した。もちろん、76cmからの落下試験にもクリアしているほか、TPU自体も手に馴染みやすくつかみやすい素材になっている。
壊れないためには衝撃に強いだけでなく、滑りにくく、落下させないことも重要だ。西村氏は、角度が20度の「傾斜台」にdynabook K70を置いて、端末が滑り落ちないことを実演しくれた。この「20度」というのは、児童生徒が机の上にPCを置いたまま両手で机を持ち運ぶときの角度を想定したものだという。
また、授業中に机の上でPCと教科書、ノートを広げると、PCが机の端に移動して落下するケースがある。dynabook K70では、重量バランスを調整して机の端でも落下しにくく、ディスプレイを開いたときに後ろに倒れにくい設計とした。さらに、ディスプレイの誤装着が起きにくいよう、児童生徒がタブレットを確実に装着できるキーボードドックに構造が改良されたのもポイントだ。
なお、dynabook K70は、第三者認証機関による米国防総省が制定する「MIL規格」に準拠した過酷な耐久テストを実施予定としている。
日常的に使う「文房具」として操作性やデザインにもこだわる
dynabook K70の魅力は「子ども目線」にこだわって開発された端末であること。ゆえに、児童生徒が日常使いするうえで扱いやすいよう細かい部分に配慮されている。
まずは、持ち運びやすさ。キーボードドック接続時の本体重量でも約1,097gと軽く、さらにディスプレイのみの重量は約590gと軽量化を実現している。サイズも約248.5mm(幅)×約185.5mm(奥行)とB5サイズの教科書とほぼ同じ、手軽に扱えるコンパクトサイズで机の上やランドセルの中でもかさばらない。
西村氏は「近年、子供たちのランドセルが重くなっていますが、dynabook70ではタブレット部分だけを持ち帰ることができるので大幅に重さを減らすことができます」と語る。
また、普段から繰り返し利用するキーボードも、強い力を加えてもキートップが外れないように突起(アンカー)を設けた。打鍵感のあるキーボードで、キートップの印字も見やすいよう視認性に配慮されている。
ペンについてはオプションとなるが、充電式アクティブ静電ペン2を用意。ペン先を正確に検知して、小さな文字も思い通りに表現できるという。キーボードドック右側面にペン収納スロットを用意しているので、タッチペンの紛失を防ぐことができる。
ほかにも、情報リテラシーが発達段階にある児童生徒が使う端末であることを考慮して、カメラの撮影時はLEDライトが点灯するよう配慮されている。これは盗撮を未然に防ぐことを目的としており、遠くからでも撮影していることがわかる。本来であれば、こうした事態が起こらないことが理想ではあるが、不適切な使い方から児童生徒を安全に守ることも重要であり、この機能が実装された。
さらに西村氏は、「dynabook K70は、温かみのある文房具としてのデザインにこだわった」と話す。これも学校現場からのフィードバックによって実現したもので、無機質なデザインではなく、子供たちがPCを使いたくなるような親しみのあるデザインにしてほしいと要望があったいう。製品発表以降、現場からの反応も良く、EDIXで製品を見た来場者からの評判もいいようだ。
アクセシビリティへのアクセスを容易に
dynabook K70は、低学年の児童生徒や個別最適な学びへの対応として、アクセシビリティの画面へ容易にアクセスできるようタスクバーに独自のアイコンを設けている。
これは、Windows 11の[設定]に用意されている[アクセシビリティ]の機能をタスクバーからすぐに呼び出して、児童生徒自ら文字の大きさやマウスポインターのサイズ、コントラストなどを変更できるようにしたもの。児童生徒によっては、Windowsの設定画面までたどり着くことが難しいことから設けられたという。
教室には多様な児童生徒がいて、学びやすさはそれぞれ異なる。「児童生徒が先生に相談しなくても、自分で使いやすい設定に変更できるようタスクバーに設けました」と西村氏は語る。
最大24時間の駆動時間で約979gの教員用モデルを用意
教員用PCには、本体の薄さが17.9mmで軽さ979gの「dynabook V83」がラインナップされており、CPUは第13世代インテル Core プロセッサーから選択可能だ。
メモリーは最大32GBで、ストレージは最大512GBを搭載可能。ベースモデルによっても異なるが、最大で24時間のバッテリー駆動を実現している。タッチパネル付き13.3型のディスプレイは360度回転する2軸同時ヒンジを採用し、見やすい角度を保つことができる。アクティブ静電ペンが付属し、他機種では省略されることも多いmicroSDカードスロットを搭載する。
本体は、マグネシウム合金を場所によって使い分けて軽量化と堅牢性を両立。底面や天面のほか26方向からの落下テストなど、MIL規格(MIL-STD-810G)に準拠したテストをクリアしている。
長く安心して使ってもらえるPCを提供したい
西村氏はGIGA第2期に向けて、「共同調達による大量導入にも対応できるよう、現在、工場の生産体制を強化しています」と語る。現場での端末導入が安心して進められるよう、最大限に尽力したい考えだ。
また、dynabook K70についても、現場で安心して使ってもらえるように、スタイルを変えず、長く使い続けられる製品として提供していきたいと西村氏。GIGA第2期の製品開発ではデタッチャブルを継続するかどうか社内から意見も挙がったが、現場からこのカタチを望む声が寄せられ継続を決めたという。「教育現場においては安心して使い続けられることが大切だと考えており、長く使ってもらえるPCをこれからも提供していきたいです」と西村氏は語る。

























![[復刻版]国民礼法 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51UJxXmztFL._SL160_.jpg)










![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)





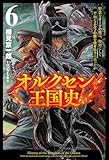

![タッチペンでいっぱいあそべる!まいにちのことばずかん1500 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/515JolaI7LL._SL160_.jpg)










